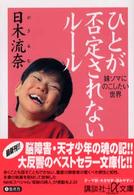内容説明
香りを通して、日本人のこころと京文化の粋を極める。世界でも稀有な日本人の美意識―その古代から現代までにいたる精神の道程を、やわらかな語り口で逍遙する「香りの文化史」。
目次
王朝からのメッセージ
香料、唐様との出会い
和魂漢才の都
王朝文学に学ぶ
もっと王朝文学に学ぶ
日本文化を育んだ二つの波
混沌の沼
東山殿御香座敷
沈水香木と六国五味〔ほか〕
著者等紹介
畑正高[ハタマサタカ]
昭和29年(1954)京都生まれ。株式会社松栄堂代表取締役社長。同志社大学商学部卒業後、渡英。昭和52年(1977)、松栄堂に入社。平成10年(1998)、代表取締役社長に就任する。社業に加え、地元京都での経済活動や環境省「かおり風景100選」選考委員などの公職、同志社女子大学非常勤講師、香道志野流松隠会理事などをつとめるほか、香文化普及発展のため国内外での講演・文化活動にも意欲的に取り組む
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
24
わたしは鼻が悪いけど、 だからこそ敏感でありたい香への 向き合い方。 特定の香りが環境として存在を 始めると、その環境にいる限り 私たちの嗅覚はすぐにその特定 の香りには麻痺し、その香りの 存在が知覚できくなってしまう (41頁)。 習い性。 この怖さ。 汚染水垂れ流しへの関心は、 集団的自衛権で麻痺させられては 日本人の社会的責任が問われる。 ボーナス当たり前の習い性も 1100兆円を返してからもらえば いいのだが、無責任にみえる。 無駄遣いの嗅覚をこそ。 2014/06/13
Mayu
4
日本文化、と一括りに考えてしまいますが、内外の社会的背景の影響を受け、時代とともに変遷してきた様子がお香を軸にわかりやすく解説されていて、とても勉強になりました。源氏物語で描かれているお香の意味や、香道の様々な楽しみ方、友好の証として海を渡った香箱のストーリーなど、興味深い話題はもちろんですが、著者の謙虚な学びの姿勢に一番感銘を受けました。伝統を学び、耕すことと、時代の変化に常にアンテナを張り、本質的に人々が求めていることや、解決すべき問題を分析することを両立されているように感じました。何度も読み返す価値2019/07/28
Noelle
2
タイトル通り、古来以来 香が日本人の文化の中で育まれ、浸透していったその歴史が詳細に描き出されている。平安の薫物香から室町時代を経て聞香へと変わっていった経緯が日本史の中の文化の変遷と共に考察され、今に繋がっていることがよくわかる。口絵にある絢爛たる香道具や、聞香の様子が描かれた浮世絵など、世界中に拡散した 香にまつわる美術工芸品がたくさんあるのだろう。まだまだ日本では他の美術品に比べ認知度が低いのは残念だが。茶道の七事式との関連や「香組箱」「耳香道具」のこともお香やさんならでは考察がとても興味深い。2015/11/11
ぼたん
2
平安の香(薫物)から室町(香木)の香へ変わっていった。日本では取れない貴重な香木を一本ずつ吟味していくようになる。しかし、平安の宮廷文化の影響力は強く、源氏物語にちなんだ組香が考案され、婚礼調度にも源氏の意匠が使われた。2013/03/08
kinaba
2
直接香の話と言うよりは香の人による日本史、という趣もある。しかし、他の"日本のものになった"文化と比べて一貫して輸入品であった、という視点はなるほどなあ。2013/01/20