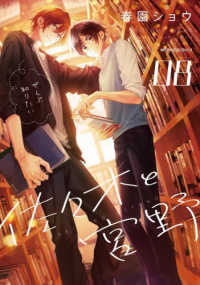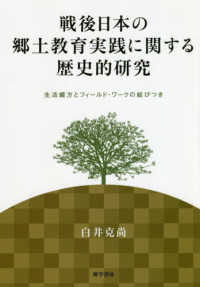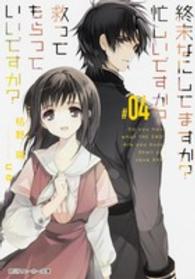内容説明
信じられないほど無知!ローマ法王はイギリスのパリにいる!?日本は第二次世界大戦の同盟国だった!?プーチンって誰!?アメリカの将来はどうなってしまうのか?―国を憂う大学教授がU‐30世代のあまりの無知ぶりを警告。
目次
第1章 若者の大半が知識不足
第2章 新種の書籍恐怖症
第3章 ディスプレイ・タイム―駆逐される読書習慣
第4章 オンライン学習と「学習しない習慣」
第5章 教師・指導者の背信行為
第6章 知識は民主主義を推進する
著者等紹介
バウアーライン,マーク[バウアーライン,マーク][Bauerlein,Mark]
エモリー大学英語学教授。カリフォルニア大学で英語学博士号を取得。2003~05年、全国芸術基金(芸術活動を財政支援するための連邦政府機関)で研究・分析部門担当の理事。ウォール・ストリート・ジャーナル紙、ワシントン・ポスト紙などに寄稿。アトランタ在住
畔上司[アゼガミツカサ]
1951年長野県生まれ。東京大学経済学部卒。日本航空勤務を経て、現在ドイツ文学・英米文学翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
プラス3
1
アメリカ版「下流志向」、「分数のできない大学生」といったところか。
aki
1
すっげおもしろかった。自分と妹と重なる部分があって、共感できた。でも日本はまだまだ読書を大切にしようという風潮があるからまだましかな。でも日本もけっこうやばいと思う。2010/05/05
shushu
0
テクノロジーの発達は未熟であることを許してしまう、ということかな。いくらテクノロジーが発達しようが目は2つ、一日は24時間。ディスプレイを見ていたら読書はできない。ネットにアクセスしている間は、他のことを経験できない。そして技術の進歩は、人間のある種の能力を低下させる。文字が一般的になると語り部の能力は失われた。要するに多くの人は、能力の内容は変わるが総量は変わらないのだろう。ところで自己評価が高いと出来が悪い、というのは内田樹の「下流志向」を思い浮かべたら後書きで町山智浩も言及していた。2013/09/28
taitaiyaki
0
若者が本を読まないのは世界?の常識だったんですか。だからどうなの?2012/08/19
ur
0
読書推しがいささか強かったと思うが・・・自分の悩みが少し晴れた。なぜ自分がばかなのか悩んでいたけど、SNSの影響が一番だってわかった。テレビやインターネットなどのテクノロジーが発展して、若者が画面に向かうようになったから馬鹿になった、というのには賛成だ。しかし、それに対して反論があるのには・・・驚いた。反論の内容も「IQの得点が上がった」とか「認知力が上がった」・・・とか。知識は上がったどころか低下してるだろ!って思った。とにかく、ほかにも賛同できる点がたくさんあったし、面白かった!2012/05/24