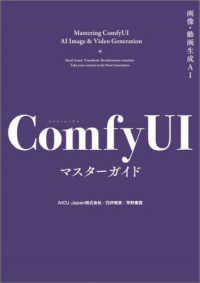出版社内容情報
脳細胞が一番活発に活動している赤ちゃん期、集中力、想像力などの基となる「聞く力」をつけるのはこの時期がポイントなのだ。子育てを後悔しないための一冊。
内容説明
赤ちゃんの潜在能力を引き出すために元お茶の水女子大学附属幼稚園園長の熱い提案。
目次
第1章 ゼロ歳児の教育を考える
第2章 みんな、絶対語感をもっている
第3章 意味より先に「カタチ」を覚える
第4章 スキンシップで子どもを安心させる
第5章 上手にほめて才能を伸ばす
第6章 耳をよくすれば頭がよくなる
著者等紹介
外山滋比古[トヤマシゲヒコ]
英文学者、評論家、文学博士。1923年生まれ。東京文理科大学英文科卒業。お茶の水女子大学名誉教授。専門の英文学をはじめ、思考、エディターシップ、言語論、教育論など、幅広い分野で、独創的な研究を続けている。幼児教育に関する著書も多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
hori-chan
3
・子供がウソをつくことの価値。 ・耳で賢くなる。 などが気付きです。2025/03/05
ちいちゃん
3
子供の聞く力を育てる重要性を説いた本。親の語りかけが大事。2016/04/13
てふてふ
3
傾聴する力を育てること。私もこれ苦手だって、言われて初めて意識した。メモを取りながら聞くことはあまりないけど、言われたことを整理するのに頭の中だけではできなくて紙に書いたりするなぁ。母乳語(具体的)と離乳語(抽象的)の説明に納得。国語教育の話も、まさに私のことかと思いました・・・文学作品の抽象的な未知の世界を、ことばをもって理解すること。2015/06/30
shizuca
2
2012年に出版されたにしては、内容が古い。昔の人は偉かったわかっていた、という言葉がでてくるけれど、昔っていつ? 江戸時代? あと、内容が自分の主張と思い込み(ではないかと思った)で書かれているからか、同じことの繰り返しで、昔のにほんじは偉かった、今はいかん!と。少子化にしても、もとは戦後の集団就職で若いものが東京行ってそのまま家庭を都市でもったことで核家族化がすすみ、戦前に普通だった3世代同居などが減った。高度経済成長により父親は企業戦士にならざるを得なかった…のような具体的な説明もなかった。驚き2020/06/28
るい
2
確かに私たちは視覚を重視しすぎている!テレビやスマートフォンが普及して、ますます視覚重視になったような気がする。話が聞ける子どもを育てるためには、大人自身が話を聞くべきだよなあ。反省である。2018/07/08
-
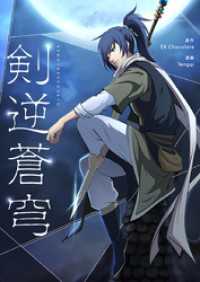
- 電子書籍
- 剣逆蒼穹【タテヨミ】第289話 pic…
-
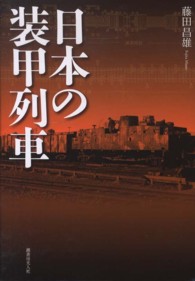
- 和書
- 日本の装甲列車