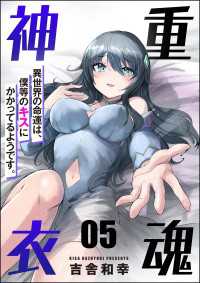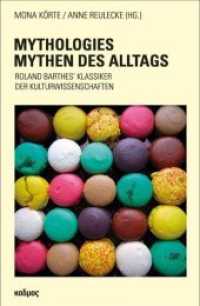出版社内容情報
貨幣とは何か、資本主義とは何かを鋭く問い続け、従来の経済学の枠組みを超える新しい理論を構築してきた第一人者による、知的魅力あふれるエッセイの集大成。
内容説明
文学や映画や、絵画、リーマン・ショックやビットコイン、日本の近代化の問題に人文社会科学の危機―貨幣や資本主義を根源的に探究してきた理論経済学の第一人者が、縦横に語ったエッセイ集。
目次
1 エッセイ四編
2 半歩遅れの読書術
3 時代の中で考える1―『思潮』から(二〇〇〇‐二〇〇四)
4 時代の中で考える2―『経済教室』その他から(二〇〇八‐二〇二三)
5 時代を超えて考える―『貨幣論』以降の研究から
6 時代の中で自分を振り返る
7 亡き人を悼む
著者等紹介
岩井克人[イワイカツヒト]
1947年生まれ。東京大学経済学部卒業。マサチューセッツ工科大学Ph.D.取得。イェール大学助教授、プリンストン大学客員准教授、ペンシルバニア大学客員教授、東京大学経済学部教授、国際基督教大学特別招聘教授等を経て、神奈川大学特別招聘教授、東京大学名誉教授、日本学士院会員。2023年、文化勲章受章。著書に、Disequilibrium Dynamics(Yale University Press、日経・経済図書文化賞特賞)、『貨幣論』(ちくま学芸文庫、サントリー学芸賞)、『会社はこれからどうなるのか』(平凡社ライブラリー、小林秀雄賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
92
著者は現在の経済学者の中では第一人者であると感じています。これはエッセイ集なのですね。若干日経新聞の「経済教室」の小論が収められているので頭の体操にはなります。さらにもう少し経済学に踏み込んだ「時代を超えて考える」ではかなり手ごたえのある貨幣論を展開されておられます。変わったところでは「半歩遅れの読書術」で「宮本武蔵」などが取り上げられていています。また「高慢と偏見」についてのエッセイも楽しめました。楽しめました。2024/10/13
逆丸カツハ
51
本当にこの人の本を読んでよかったという書き手が何人かいる。岩井克人は自分にとって紛れもなくそのうちの一人だ。この人の本に出会えて、本当に幸せだと感じている。2024/09/28
Sam
49
エッセイ集。テーマの重複も多いし凝り性のご性格ゆえか必ずしも読み易いものばかりではないが、とても興味深く読ませていただいた。中庸を地で行くようなお人柄である一方、「せめてものを考えるときは大胆に」というお言葉の通り舌鋒鋭く核心を突いていく。「フリードマンはなぜ完全に間違っているのか」なんて新自由主義のチャンピオンを相手に胸がすく分析ではないか。有名な「法人2階建て理論」に関する論文で、AIの登場とともに「ヒト」と「モノ」という2分法が修正を迫られるかもしれないという注書がとても気になった。2024/10/01
1.3manen
45
自己疎外とは、他者による批判(20頁)。批判を恐れて情報発信などできない。資本主義とは、アイデアを持つ人がおカネを持つ人からおカネを借りて、アイデアを実現するための投資を行っていく仕組み(95頁)。金持ちがアイデアを持ってればいいのだが、ビンボーがアイデアを実現する術が重要だ。産業資本主義:大量生産を可能にする機械制工場を利潤の源泉とする資本主義(157頁)。マーシャルの高弟ケインズも新古典派経済学者として出発。2025/08/05
まゆまゆ
16
2000年以降の新聞コラムなどをまとめた内容。当時からデフレを批判し、ポスト産業資本主義としてカネからヒトへの変化を指摘していたが、貨幣論を踏まえて現在のインフレ社会はどう評価しているのだろうか。少なくともしばらく資本主義経済に変わる新たな考え方は一般化しなそうだけど……2024/12/16