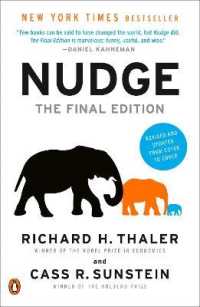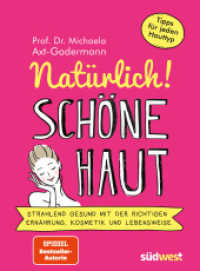出版社内容情報
O・ヘンリー賞を4度受けた短篇の名手、フラナリー・オコナーの精神の記録。死を見つめながらも、自らを作家へと育てた成長と成熟の軌跡をたどる。本邦初訳。
内容説明
死を見つめながらも、自らを作家へと育てあげた得がたい精神の記録。作家の成長と成熟の軌跡をたどる書簡集。
目次
第1部 北部行きと帰郷―一九四八年‐一九五二年
第2部 在宅日と外出日―一九五三年‐一九五八年
第3部 激しく攻むる者はこれを奪う―一九五九年‐一九六三年
第4部 最後の年―一九六四年
著者等紹介
オコナー,フラナリー[オコナー,フラナリー][O’Connor,Flannery]
1925‐1964。アメリカ南部ジョージア州で育つ。短篇の名手として知られ、O・ヘンリー賞を四回受賞
横山貞子[ヨコヤマサダコ]
1931年生まれ。京都精華大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ソングライン
17
792通のフラナリー・オコナ―の書簡の中から、友人のサリー・フィッツジェラルドが編集した273通の書簡集です。初の長編「賢い血」の出版のためのやり取りから39歳で亡くなる直前の短編集の出版への意欲まで続きます。相手はエージェント、編集者、読者、多くの友人たちで三十数人に及びます。敬虔なカトリック信者であること、繰り返す難病との戦い、自宅で育てる孔雀や白鳥、特に「善人はなかなかいない」の読者の解釈に対する返答が印象に残ります。もう一つの長編「激しく攻むる者はこれをこれを奪う」読んでみたいです。2022/03/16
sayya
5
習慣は、毎日意識的に続けることで一定のリズムとなり、自動的に何かを生み出すようになる。 オコナーは存在すること、生きること自体を習慣とすることで、徐々に高みへと昇っていった。 「毎日、同じ時間帯に、おなじことをおなじ時間だけやれば、落ち込みから自分を救うことができます。 日課は生き延びるための必要条件なのです。」2011/06/17
なつ
5
タイトルに惹かれ購入。書簡集は元々好きだ。存在することを習慣と呼ぶほど生活の中で意識する事、読書家は彼女の作品世界をその解釈の助けにするのかもしれないけど、一般的な生活のままならない病を持ち尚力強く生きようとする人ならこの言葉の意味は痛いほど身近ではないだろうか。本文中では何度か彼女のストイックな生活態度について触れられ、それが彼女の人格的な問題ではないと説明されているが、生自体に強い意思を必要とし、それを意識して生活している人は、彼女の作品を知らなくても得るものは大きい。苛烈な先人の生き様がある。2009/12/20
いのふみ
4
進行する病の中においても書き続けることを忘れなかった姿がありありとわかる。そういった姿勢や、人の世の生と死のグロテスクさをユーモアをもって描く作風で、大江健三郎と親交があるのは納得できる気がする。2021/12/13
ナディル
3
小説家フラナリー・オコナーの書簡集。作品は重厚で暗いイメージですが、手紙からはユーモアと思いやりに満ちた彼女の芯の明るさが伝わってきます。自作への言及、創作論に加え、カトリック信者としての信仰態度が清々しいのも印象的でした。時折触れられる自身の難病についてもごくあっさりしたものです。精神の明晰さを明るさを生むべく使用する方法を彼女は熟知していたように思えます。 「書くときには、自分がすべきことを、自分ができるやり方でやる」。シンプルすぎるほどですがハッとさせられました。2023/06/11
-
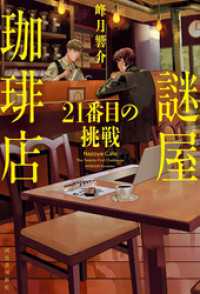
- 電子書籍
- 謎屋珈琲店 21番目の挑戦
-
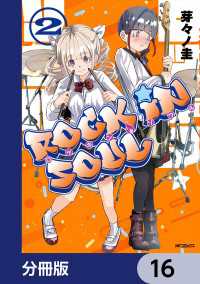
- 電子書籍
- ロッキン・ソウル【分冊版】 16 アラ…