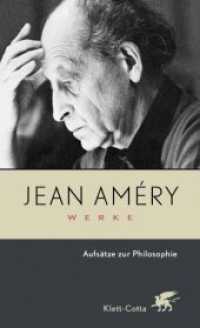出版社内容情報
学校には、人類の叡智や希望が詰まっている。でも巧妙な出来レースも仕組まれている。さまざまな教育現場を見てきたプロが教える、学校をサバイブする方法。
内容説明
ルールやべき論で子どもたちを縛り、思考停止した大衆を社会に送り出すクソみたいな装置という面が学校にはある。思考停止した大衆はルールを求める。ルールはひとをますますバカにし、バカはさらにルールを求める。バカとルールの無限増殖ループだ。
目次
第1章 なぜ勉強しなくちゃいけないの?
第2章 時代は変わってもひとは変わらない
第3章 出来レースだらけの競争社会
第4章 なぜ大人は髪型や服装にうるさいのか?
第5章 「いい学校」より「面白い学校」を探せ
第6章 青春の舞台としての学校
第7章 「理想の学校」なんていらない
著者等紹介
おおたとしまさ[オオタトシマサ]
教育ジャーナリスト。1973年東京生まれ。リクルートで雑誌編集に携わり、2005年に独立後、数々の育児・教育誌のデスク・監修・企画・編集を務め、現在は教育に関する書籍執筆および新聞・雑誌・webメディアへの寄稿を行う。テレビ・ラジオなどへの出演や講演も多数。心理カウンセラーとしての活動経験、中高の教員免許、私立小学校での教員経験もある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
69
面白かった。著者は教育ジャーナリストのおおたとしまさ氏。学校に詳しい人という立場から、学校に通う意味だとか、学校で味わう様々なストレスの対処法だとか、学校の選び方などを思いつくまま自由に語った一冊。教科書はフリーズドライ食品と同じで、教師が教科書の話を膨らませることで初めて美味しい食材となるとのこと。また、偏差値のからくりとして入学の定員を半分にすれば簡単に偏差値を上昇出来ると聞いてなるほど~と思いました。2024/03/23
みねね
37
毎度のことながら教育関係の新書を読むと「よく言ってくれた!」と「そんだけ無責任に言えたら気持ちいいだろうな〜」が混在する感覚がある。この矛盾の感が拭えないことにはよく働くのは難しくて、そもそもよく働こうと思っている時点で「今日的には」よくない働き方しかできないのだ。自分がやりたいような授業をして、生徒が勝手に吸収して育っていくのは理想論である。どれだけ楽しく面白い授業でも、生徒の睡眠時間3時間で聞いているだけで教室が暑いのなら、生徒の意識はほとんど保たないだろう。そして何より楽しく面白いを決めるのは生徒。2024/10/27
りょうみや
25
おおた氏がブログで「80冊以上ある私の本の各エッセンスをぎゅーっと176ページに凝縮した濃厚な自信作」と紹介していたが、まさにその通りで著者のファンにはたまらない一冊。これまで多くの著作で味わった著者の教育哲学が詰まっている。濃厚な代わりに著者の本業のルポによる具体例は最低限のため凝縮され過ぎているかもしれない。ちくまプリマーの本来の対象である高校生向けというよりはやはり著者の本を読んできたファン向け。2024/01/19
さとみなおと
11
教育関係者、中高生にも読んでほしい。特に共感した箇所を引用。「くれぐれも、狭い教室の中だけが世界だと思わないでください。教室の中が息苦しい、生き苦しいと感じたら、中高生だってどんどん外に目を向けてください。それだけで心持ちが変わるはずです」2024/02/16
Asakura Arata
10
著者の今までの著作の総まとめの本なので読み応えがあった。DMNと瞑想、センスオブワンダーは、瞑想箱庭療法に通じるところだな。小生は、学校におかしさを感じていながらも、従順なフリをしてやり過ごしてきたクチなので、今その反動が出ている。学校に文句を言える立ち位置でもあるし。2024/02/23
-
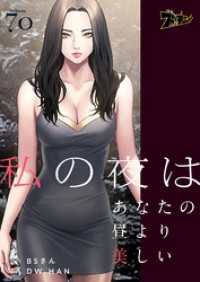
- 電子書籍
- 私の夜はあなたの昼より美しい【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- レベルMAXのAIロボットとSSS級の…
-

- 電子書籍
- アイカギ【単話】(47) モバMAN
-
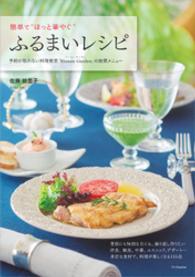
- 電子書籍
- 簡単で“ほっと華やぐ”ふるまいレシピ―…