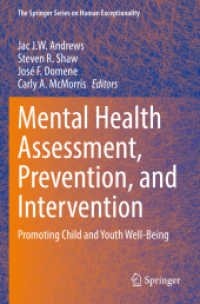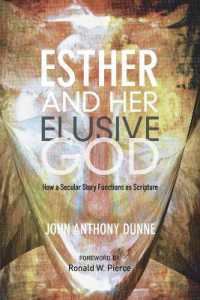出版社内容情報
意識の本質とは何か。私たちはそれを知ることができるのか。脳と心の関係を探り、無意識に目を向ける。自分の頭で考えるための入門書。解説 玄侑宗久
内容説明
21世紀はしばしば「脳の世紀」と呼ばれる。実際、急速に進展した脳科学が、ヒトの認識と行動を脳の観点から次々に解明している。しかしそれによって私たちは、ヒトとは何か、それがわかるのだろうか。脳と心、意識の関係を探り、無意識に目を向ける。「意識の科学」が緒に就いた90年代、若い読者に向けて書かれた「自分の頭で考える」ための入門書、待望の文庫化。
目次
第1章 脳は何をしているのか
第2章 脳と心の関係
第3章 脳と遺伝子
第4章 知覚と運動
第5章 脳の中の現実
第6章 意識と行動
第7章 意識とことば
第8章 意識の見方
終章 意識と無意識
著者等紹介
養老孟司[ヨウロウタケシ]
1937年神奈川県鎌倉市生まれ。62年東京大学医学部卒業後、解剖学教室へ入る。95年東京大学医学部教授を退官。現在、同名誉教授。『からだの見方』(サントリー学芸賞受賞、筑摩書房)、『バカの壁』(毎日出版文化賞特別賞、新潮社)など著書、共著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ショア
30
いやー養老先生は面白いなあ。言語は視覚と聴覚が結合して創造された。失語症の症状の違いから日本語は外国語と異なる脳の使い方をしている。ラストの意識と無意識の話し、都市では意識が無意識を排除する、だから強烈な表現である裸体で歩くことは社会で禁止されている。日本の「道」は「型」で無意識的表現を継承してきたが、近代社会は封建的だと排除するが故に若者に型がなくなりコミュニケーションできなくなっている。ヒトはどこかで自然な無意識と接してないとストレスなのだろう。やっぱり海山遊びは大事だな。2023/09/24
KAKAPO
27
「人間とは、要するにほとんど脳の働きなのである。日本で人が死ぬふつうの場合、1心臓が止まって、2瞳孔の反射がなくなって、3自発呼吸がなくなれば、医者にご臨終ですといわれる。呼吸は延髄にある呼吸中枢のはたらきで生じる、脳が完全に死ぬということは、延髄も死ぬということで、それなら呼吸も止まるのである。」2017年末、父の容体が悪くなってから亡くなるまでの期間に読んでいたので、「われわれの脳の働きである意識が主観であるということ、社会はじつは脳によって作り出された世界であるということ」を深く考える機会になった。2018/02/03
canacona
26
脳と意識についてのあれこれ。養老先生の一見優しい口調で語られるので、わかった気になるけど、実際のところは難しい。ページ数は多くない本なのに、内容がみっちり、読むのに時間がかかりました。そして結局わからないまま。そりゃそうだ、まだ答えも出ていなくて正解がないんだから。だからこそいろんな意見があって、考え続けるのが学問なんだろうな。2023/04/09
Lee Dragon
18
入力(脳)と出力系(筋肉)の話は物理的な出力、以前はソフト的(教育)で行われていたものが、今はではハード(遺伝子等)として変わる時代がやってくる。最終的に我々が評価軸としてるのはハードの面であるので、これにどう対応していこうという話が出てきた。ハードの変更を人は忌避するというのが心理的傾向にあるようである。そりゃそうだ、人の評価軸は分かりやすいハードになっているのだから。2023/05/28
ネコ虎
8
全く面白くない。読者に分かってもらおうと思って書いていない。養老の友人である池田清彦氏も結構難しい本を書いているが、難しいこともなるべく分かってもらうような努力がうかがわれるが、養老孟司にはそれがない。総じて養老の本は分かりにくいものが多いが、分かってもらおうという気がないからだと思われる。2023/07/15