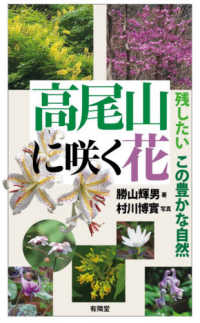出版社内容情報
内容は後日登録
内容説明
1868‐72年、著者がスイスのバーゼル大学で行った講義は伝説となった。普仏戦争などの大国間紛争が起こりナショナリズムが台頭する中、著者は西欧の政治的状況を俯瞰し、国家、宗教そしてヨーロッパの伝統文化について根本的考察を展開、また同時に権力の持つ悪や、自然諸科学の進歩への不信、人間生活における利便性が孕む危険など、世界が抱える不安定要素をいち早く指摘した。この講義に基づく本書は、来るべき世紀の社会的危機と頽廃の予兆を察知して警鐘を鳴らした、古典的名著。ブルクハルト翻訳の第一人者の新訳により、19世紀の香り高い文明論が現代に蘇る。
目次
第1章 序論
第2章 三つの潜在力について
第3章 相互に制約を受けている六つの状態についての考察
第4章 歴史における危機
第5章 個人と普遍(歴史における偉大さ)
第6章 世界史における幸と不幸について
著者等紹介
ブルクハルト,ヤーコプ[ブルクハルト,ヤーコプ][Burckhardt,Jacob]
1818‐97年。スイスの美術史家・文化史家。ベルリン大学で、歴史家ランケと美術史家クーグラーに学ぶ。1858年から35年にわたってバーゼル大学教授として歴史学、美術史を講じる
新井靖一[アライセイイチ]
1929年生まれ。早稲田大学名誉教授。専攻、ドイツ文学・西欧文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
手に入れた本の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
呼戯人
7
大学時代、ドイツ語の演習で読んだ本。歴史は、国家と文化と宗教の力関係で様々な類型が生まれるという超越論的な歴史哲学を展開して、新鮮な古典。ブルクハルトの歴史家としての慧眼は、どこまでも広く深く、イタリア・ルネッサンスという時代そのものを発見するという偉大な業績が残っている。マルクスの経済決定論とはまた異なった素晴らしい歴史哲学の書である。2015/06/29
ゲニウスロキ皇子
7
あまりよくわからなかった…思い返せば出身高校は教育困難校で、押し並べて授業が進まなかった。クラスは猿山と化し、教諭の声は無数のエテモンキーの雄たけびにかき消されていた。特に世界史は惨憺たる有様で、3年間の授業で新大陸を発見するに至らなかったのだ。ああ意欲に燃ゆることすらも叶わぬコロンブスの切なさよ。人のせいにするのはよくないと分かっている。だが、父と母よ、許してほしい。あれで勉強ができるはずはないだろう。おかげさまで、世界史の知識は微々たるものである。畜生、わからなかった言い訳にここまで書く阿呆がいるか!2011/10/27
壱萬参仟縁
2
「中央集権を排し、地方分権化を行なうことが全然見込みがないということであり、地方の生活や文化生活に有利になるように権力を自発的に制限させることにまったく望みがないということ」(p.170)。これは、現代日本の懸案課題に相当するような、世界史からの教訓に思える。文庫であるが、大部な一冊。また借りてきたが、「『幸福』とは、一般によく使われることによってすり減ってしまい、神聖さを失ってしまった言葉である」(445ページ)。あまりに安易に使い過ぎか。殊に3.11後は手垢にまみれているか。評者は10年前意識したが。2012/05/17
tatsuki
0
読了まで時間がかかった。西高東低。辛辣。冷徹。ティムールに対する評価が笑っちゃうくらい低い。しかし、私にとっての近代史がブルクハルトにとっての現代史で、現在の情勢と比較しても精度が高過ぎで打ちのめされる。歴史学を歴史哲学から分離しなければならぬ、という視座も好き。訳者後書きで、何となく独よりに見えた裏事情も知るなど。ヘタリアファン必読の書であろう…は言い過ぎか。2012/04/21
sgnfth
0
面白かったから後で買う2010/02/01