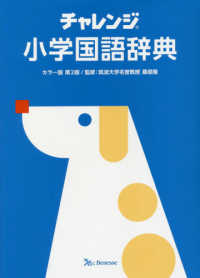内容説明
古来日本人は、たえず海外から新奇な意匠を積極的に取り入れ、風土はなじませ、育んできた。その繰り返しによって、いつしか日本の美の基準を目に見えるかたちとして生みだした。飽くなき情熱で円形に収めた家紋、吉祥をねがう宝尽し、割付文様の青海波や亀甲つなぎなど、和風文様はそのどれもが本来無機的な幾何学文様でさえ、時の流れに感情を添わせ、季節のうつろいそのものを美とする花鳥風月のこころにつながっている。日本人が、もっとも好み、美しいとして表わしてきたかたちに和風のありかを語らせ、その独自性とはなにかを、豊富な極細密画とともに個別の主題に沿って解き明かす。
目次
第1章 天象(遙かな瑞祥のかたち)
第2章 地獄と業火(こころの炎)
第3章 浄土と秋草(もののあわれ)
第4章 蓬莱文様(鶴は千年、亀は万年)
第5章 有職文様(純和風ここに始まる)
第6章 家紋(身近な風物、究極の洗練)
第7章 宝尽し(吉祥をねがう)
第8章 飾り(魂のかがやき)
第9章 花鳥風月(季節の移ろいに、こころ澄む)
第10章 割付文様(名付けでいのちを得るかたち)
著者等紹介
樹下龍児[キノシタリュウジ]
1940年、旧満州奉天に生まれ、北九州に育つ。1964年、東京人形町に文様デザイン事務所を開設。染織図案から建築室内装飾まで、デザイン実務に携わる。数多くの個展を開催。1995年から茶道雑誌月刊『遠州』に日本の伝統文様を連載中。現在「オーナメントアート龍事務所」を主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya