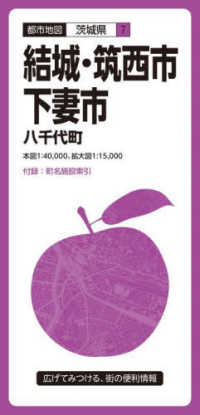出版社内容情報
「ありふれたものをおいしく食べる」。七〇年代以降、資本流入や流通の変化による「食」の激動の中で、自分の「めし」をハンドリングするための、生活めし論考。
内容説明
戦後から高度成長へのシフト転換する70年代からこのかたの、食卓にならぶ料理と台所の激変。それは、食の現場への資本の流入や保存技術の発達、流通の変化などを無視しては語れない。その流れをたどる一方で、日本の誇る「日本料理」は、その変化になぜ対抗・対応できなかったのかを思考し、翻って日々を暮らすことと料理との関係を考える、戦後日本の「生活めし」論。
目次
第1章 激動の七〇年代初頭、愛しの魚肉ソーセージは
第2章 クックレスの激動
第3章 米とパン、ワインとチーズの激動
第4章 激動のなか「日本料理」はどうだったのか
第5章 さらに日本料理、食文化本とグルメと生活
第6章 生活料理と「野菜炒め」考
第7章 激動する世界と生活料理の位置
著者等紹介
遠藤哲夫[エンドウテツオ]
1943年新潟県六日町(現・南魚沼市)生まれ。通称「エンテツ」。「大衆食堂の詩人」といわれる。職業転々のち、1971年より食品・飲食店のプランナーの道へ進み、独自の料理論・文化論を展開した食文化史家の江原恵の影響を受け、江原との共同活動等を行う。1990年代から、大衆食、大衆食堂についての著述業を行い、フリーライターに(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤枝梅安
59
美味しい大衆食堂の紹介も入っているのかと期待したのだが、そういう記述はなかった。「食」にまつわる「戦後の激動」を一人称で語る部分が多く、さらに引用が加わって、特に前半は読みにくい印象。後半の「野菜炒め」あたりからトーンアップしてきて興味深く読めた。「食」に関する政府の施策の欠点を厳しく追及している点は評価したい。「食」以外の面でも、結局は消費者が正しい選択をしていくことが産業全体の正常化・活性化に繋がることは、頭で理解できても、人間の脳や体は「欲望」で動くのだなぁ、と思い知らされることが多い。2014/03/05
bapaksejahtera
16
食通や名店に蔓延る権威主義を批判的に論ずる。儀式料理から本膳、懐石料理の流れのみを日本料理とし、大衆の日常茶飯である食事の「おかず」は、その対象としない議論に対し「日本料理とは日本の料理一般とは異なるのか」と斯界の権威の空理空論を揶揄し、「生活料理」の観点を主張する。私も大いに同感する。調理場における安定的強力な火力の出現による家庭料理の変化、低温流通やレトルトの出現等興味深い指摘もあるが、大衆食堂と家庭調理の何れが本書の主題か判然とせず、後半やや議論が流れる。「おれ」を用いる論述は暴論の隠れ蓑にも思えた2023/12/08
小鈴
15
新書なのにオレが主語の文章。めしのオカズは「日本料理」なんかではなく、日本料理体系に位置づけられてすらいない衝撃。天ぷらも寿司もそばも「日本料理」ではない!。日本料理とは酒席料理であり料理屋料理のこと。家庭のご飯や大衆食堂の料理を「生活料理」と命名し、生活料理について語った本。生活料理を日本料理の体系から排除していたことが日本料理が食べられなくなった要因だとか。エンテツは熱く語る。6章の野菜炒めがよい。野菜炒めはガスの普及が進んだ戦後に広まった料理!戦前にはなかったのだ。オカズの歴史は奥深し。2013/11/29
ようはん
13
著者の語り口は割と好き。野菜炒めは戦後に火力を確保できるガスコンロが一般家庭に普及してから登場したというのが1番面白かった。2021/01/18
森
12
図書館で借り、急いで斜め読みです。新書で、書き手が「おれは…」という文章にまず驚い…、中略、という、なかなかのもんだと思う。ハズと思いましたが、割と良い本でした。f^_^;2018/09/19