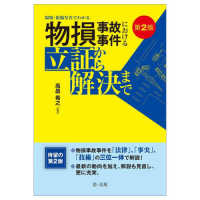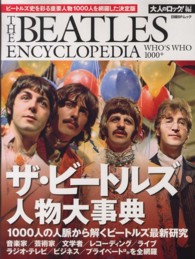内容説明
エアコンを使えば温暖化を招く。洗剤を使えば河川の富栄養化が起こる。肉食はエネルギー的にムダの多い贅沢だ。わかっちゃいるけど、やめられない。かくして環境破壊は、今世紀最大の問題のひとつになった。なぜ私たちは「わかっちゃいるけどやめられない」のだろうか。本書では、進化心理学の立場から、ヒトの認知能力と環境との関わりを検証し、環境破壊は人間の「心の限界」がもたらしたものという視点を提示する。生物学からみた、まったく新しい環境問題の書。
目次
第1章 「環境」とは何か
第2章 人間はどのような動物か
第3章 心の進化
第4章 環境の認知
第5章 公共財を巡って
第6章 進化と環境倫理
著者等紹介
小田亮[オダリョウ]
1967年徳島県生まれ。東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程修了。京都大学霊長類研究所教務職員、名古屋工業大学講師などを経て現在、名古屋工業大学大学院工学研究科助教授。専門は自然人類学、比較行動学。霊長類を対象に心と行動の進化について研究している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shiorist
6
ヒトの心理や行動は結局のところ身体含む環境に強く呪縛されていて、環境を変えないとどうにもならないもんだってことや、本来目の前の具体的な事象しかとり扱えない性質があるってことが解説してある。広く浅く知識を得るためには良いかと。2010/11/24
ユウユウ
3
身の丈を知るべきか2025/09/02
こーじ
1
若かりし日の私にとって、本書はすごく意味のある本となり、ここから科学的思考に一石を投じていただいたと言えます。/タイトルと内容は、相容れないと感じます。当時の私は、人間の『業』に関心がありました。生きている以上避けては通れない原罪につながると感じ、本書を手にしました。しかし書かれている内容は、生物学に基づくヒトの特性や、心理学のような内容。それまでに触れたことのない思考で、とてつもなく心が躍りました。/リチャード・ドーキンスらの書籍を手に取るきっかけも、本書から。もっと評価されてもいい本だと思います!2006/08/01
オランジーナ@
0
環境問題を進化心理学などの観点から考察されている。情報量が多くて結局言いたいことはよくわからなかった。環境問題を身近な話題として認識するのは中々難しいってことはわかりました。2015/10/18
おる太
0
環境哲学について生態学や進化論からアプローチしている本書。世代間倫理や自然権、資源を無駄使いしないといった、頭ではわかっているけど、なかなか解決しようとできないことは、人間の認知の仕方、規模の限界のせいでうまく認知できてないっぽい?!なるほどなぁー。もっと人間が認知しやすい範囲に変換して考えないと、環境問題なんかもリアルに感じ取れないのかもしれない。2015/01/19
-
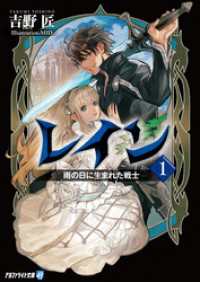
- 電子書籍
- レイン1 雨の日に生まれた戦士 アルフ…