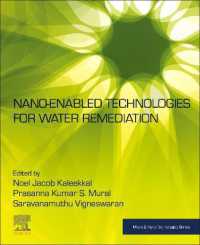内容説明
中山間地域が直面する諸問題を鋭く指摘しフィールドから提言する。過疎化・高齢化、耕作放棄、獣害、景観論議、整備技術、災害対策、農政のあり方…伊那毎日新聞(2004~08年)連載の「よみがえれ農業・農村」未掲載文を含む66のコラムをまとめた待望の続編刊行。
目次
1 山村の村おこし
2 姨捨棚田を考える
3 坂折・平原・長谷の棚田の整備から
4 棚田の草刈りを考える
5 災害・震災への対応―自らの防災を考える
6 農山村の景観を考える
7 森林・獣害・土地改良・中山間地を考える
8 最近の出来事から
著者等紹介
木村和弘[キムラカズヒロ]
信州大学農学部教授。1946年、神奈川県生まれ。信州大学農学部森林工学科卒業。農学博士。専門は、農村計画、農業土木学。山間地域の農地の荒廃化対策や、傾斜地水田の圃場整備技術の開発などの研究に従事。各地の棚田の保全・整備計画に関わる。1998年「再区画整理を考慮した傾斜地水田の圃場整備技術の開発」で農業土木学会学術賞、2005年『信州発棚田考』で農業土木学会著作賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
0
農家民泊の修学旅行生(p.30~)。飯田市は環境文化都市だが、文化としての学習活動の意義が中山間にある。他にも、急傾斜地の景観を維持するには畑を耕す以外ない、同市上村。新潟県の山古志村(現、長岡市)の復興模様も調査されている。景観形成住民協定(p.155~)は、中山間でも地方都市の伝統的町並み保全と同様、推進されれば住民も観光客も双方にメリットがありそうだ。中山間単独での対策と、他の地域と共通する対策と、相乗効果を期待するといいのではないか? 今後、人口減少で少ない人間がマルチに活躍が求められる。2012/06/21
go
0
#続・信州発棚田考 #信州大学農学部 #伊那毎日新聞 2004~2008年連載のコラムをまとめた続編。2019/10/05