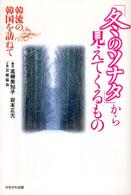内容説明
猛暑や豪雨が多くなったのは地球温暖化のせい?世の中そんなに単純ではありません。刻々と移り変わる気象をどうやって切り取り、観測データから何が見えてくるか。数字で読み解く気象の世界。
目次
第1章 大雨は夜に多いか―統計で見えてくるもの
第2章 地球温暖化を捉える―気候変動の検出
第3章 「ゲリラ豪雨」はヒートアイランドのせいか―統計と因果論
第4章 気象台の気温と街の中の気温―観測データの代表性
第5章 データの信頼性を生み出すもの―品質情報の大切さ
第6章 平均値、変動、極値―統計の基本事項
著者等紹介
藤部文昭[フジベフミアキ]
1955年愛知県に生まれる。1977年東京大学理学部物理学科卒業。1983年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士。同年、気象庁入庁。新東京航空地方気象台、気象研究所予報研究部を経て、2013年から気象研究所環境・応用気象研究部長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TA
20
1章では『大雨は夜に多い』という主張をする。過去35年1000地点のアメダスによる雨量データから、大雨(ここでは6時間降水量200mm以上、これがどれだけの量かというと、空の円筒形のバケツを外に6時間置いとくとバケツに貯まる雨水が深さ200mm以上になるぐらいの雨)が降った回数を時間別にまとめると、確かに、18〜3時の夜間に大雨になる回数が多い事実があった。しかし、こういった傾向(夜に大雨が多い)が出たことを統計的にしっかり主張するには傾向が偶然なのかどうかを検定によって調べる必要がある。2018/03/23
Aby
5
タイトルから内容が丸わかりであるが,「気象におけるデータの統計処理」とよむか,「気象をネタにした統計学入門」と読むかは,読み手の興味の方向性によるだろう.私の知識量は統計>気象なので後者だが,興味深く読めた.◆「第6章 平均値・平均・極値」は,社会科学や安全性といった政策に関わる場でも誤解をされているところ.ほんと頭抱えてしまう.2019/10/30
ラーメン小池
4
気象に関する数値やデータを、統計的な視点から正しく解釈できるための解説本。統計的の手法自体は他の分野(社会、科学全般)と共通するものが多い。しかし気象の場合、データの入手に関し、観測頻度、代表値のサンプリング手法、日界の決め方、過去観測データとの整合など、気象特有の留意点が少なからず存在する。本書はデータ構成の前提となる「観測・観測値」の取り扱いを丁寧に解説するとともに、異常気象や温暖化を煽る記事に対しても冷静な見方を提供する。アメダスデータ等気象数値を扱う人や、気象一般に興味がある人にお勧め。2014/12/06
lo_resort
3
気象データを扱う際に知っておくべき統計リテラシーについての概説。気象現象を数字で把握することのそもそもの困難さのために、他分野よりも一層の統計リテラシーを必要となるのかなと思います。統計学的に正しくても、実際の気象現象にそぐわない場合も多々ある(終盤のグンベル分布のあたり)等、今後の研究の進展に注目したいです。2015/03/01
在賀耕平
1
台風が多かったり、大雪が降ったりするとすぐに地球温暖化に結び付けて考えるバカなお前どもに統計学の基本からおしえてやる。気象っていうのはそんな単純なものじゃねーんだよ。という感じの本。 統計学の基礎がない僕のような人間が読むと大変におもしろい。 ちなみに著者は地球温暖化を否定しているわけではもちろんありません。2014/12/29