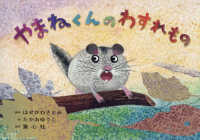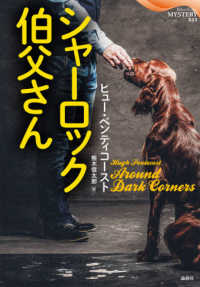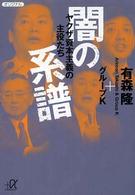内容説明
「建築家が下劣な人間であれば、崇高な建築物は決してできないであろう」…深い教養を持つ知識人であり、科学者であり、名工でもあった建築家は、建設現場の経験から専門的能力を育んだだけの単なる大工とは、たしかに異なる存在であった。
目次
第1章 新たな世界
第2章 建築家
第3章 表現手段
第4章 建設現場
資料編 大聖堂の建設者たち
著者等紹介
エルランド=ブランダンブルグ,アラン[エルランドブランダンブルグ,アラン][Erlande‐Brandenburg,Alain]
国立古文書学校卒。国立ルネサンス美術館の主任学芸員としてその創設に携わるほか、フランス国立美術館連合委員長補佐(1987~1991)、国立中世美術館学芸員長を歴任、現在、高等研究実践学院研究指導教授、古文書学校芸術史教授、国立古文書館事務局長を務めている。多くの著作があるが、なかでも新たな見解に基づく芸術史を提示した『大聖堂』(ファイヤール社、1989年)は国際的に高い評価を得た。フランス古文書学会会長でもある
池上俊一[イケガミシュンイチ]
1956年愛知県生まれ。東京大学院総合文化研究科教授。専攻は西洋中世史。東京大学大学人文科学研究科博士課程中退。86~88年フランス国立社会科学高等研究院に留学、研究に従事する
山田美明[ヤマダヨシアキ]
1968年生まれ。東京外国語大学英米学科中退。仏語・英語翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
花林糖
18
(図書館本)図版が豊富なので読んでいて楽しいけれど、凝り過ぎていて少し読み難さがあったのが残念。後半の資料編「大聖堂の建設者たち」が面白く読めた。(中古入手)2016/09/20
東雲
10
図書館本。教会建築、特に大聖堂について豊富な図版を用いながら説明された本。城壁と街の象徴となる大聖堂の関係など興味深い。材料の調達、運搬、設計、加工、建設の流れを中心として語られる。木材から石材へ移り変わりつつも、一部は木材が含まれているとか。建設主と建築家との間で交わされた契約書、プレゼンテーションで用いられた精巧な設計図や模型などが残されているが、実際の作業行程や技術面についての資料は少ないらしい。図版が入り乱れて読みづらい点もあるが、手元に置いておきたい一冊。疑問点も増えたため、関連本も読みたい。2017/05/15
void
7
【★★★☆☆】項目は細分化してるし一般読者向けということで内容は平易だが、文章自体が読みづらい。ほぼカラーだし、眺めるだけでも楽しいけど。歴史状況、建築手法・技術の変化、建築主と建築家や職人との力関係・対立・取り決め、専業化と職業意識の高まりなどなど。中世のおいて模型は(ほとんど?)使われなかったとかなんとか。そういやケン・フォレット『大聖堂』に模型は出てこなかったな(wikiによると時代考証は結構精確だそうな)。2014/01/03
金監禾重
4
暗黒と言われがちな中世ヨーロッパで、石を計画的に、精密に加工して積み上げる技術がこれほど急速に発達したことに驚く。日本で言えば寺の堂塔や城の石垣・天守閣にあたるだろうが、上への指向の強さや競争の激しさが比べ物にならない。日本の、巨大建築に永久を求めにくい地震環境も大きいだろう。さらに日本では徳川幕府が大寺院、大規模城郭だけでなく、橋梁や大型船舶の競争を制限・統制した。江戸時代に大聖堂建築のような大規模消費や石橋による交通環境の強化があれば、日本はどうなっていただろう。2019/03/17
絹子
2
久々に読んだ「知の再発見」双書。図版いっぱいで眺めていて楽しい。でも、キャプションや本文のレイアウトが凝りに凝っていて、逆に読みづらいかも。2011/09/28