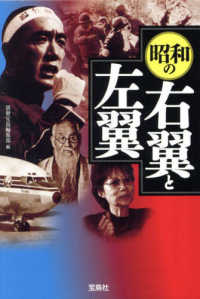出版社内容情報
【解説】
ヨーロッパ絵画の歴史において,常に時代の変革者を生み続けたスペイン。18世紀に活躍したゴヤは,その中でもひときわ高くそびえる巨人。ゴヤの生涯を作品とともにたどる。
目次
第1章 成功への道
第2章 肖像画と風俗画
第3章 失われた聴力
第4章 首席宮廷画家として
第5章 『戦争の惨禍』と『黒い絵』
資料篇 4大版画集とその世界
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新田新一
43
ゴヤの生涯を詳しく書いた本です。ゴヤの生涯はスペインの政治が目まぐるしく変化した時代で、彼は政治に翻弄されながら作品を描き続けたことが分かります。初期の作品にはルノアールのような端正で親しみやすいものもありますが、年齢を重ねると人間の暗黒面を直視したような不気味な絵が多くなります。とくに有名な「わが子を喰うサトゥルヌス」は恐ろしい絵で、夢の中に出てきたら、うなされそうです。どんな人も後ろ暗い面を心に抱えており、それに光を当てるのがゴヤの後期の作品かもしれません。2025/12/12
すずき
4
私が読んだ1991年の第1刷は表紙がかの有名な《巨人》なのだが、プラド美術館がゴヤ作ではないというレポートを出してから新しいものは自画像に差し替えたのだろう。私はゴヤというと晩年近くの「黒い絵」がまず浮かぶが、意外と明るい色彩のものも特に初期は描いており、その変遷はカラヴァッジョの色彩の変遷を連想させるところがあり驚いた。この人は幅の広い画家で仕事としてもカルトン、天井画、肖像画と手広い上に画風も技術としては新古典的なものも描くことができる。日本の(というか私の?)ゴヤ受容がいかに偏っているか理解した2019/09/30
kero55
2
面白かった。 ゴヤは、色々有名な絵を残してるけど、やっぱり面白いのは黒い絵シリーズかなあ、と思う。 後、諷刺の効いた版画とか、人間の負の部分が迫力ある。金銭的にお金がないと表現の自由は許されないていうリアリストだし、基礎もきちんと勉強するてとこが凄い。後年、 本人が大病で聴力を失い、内乱や戦争、異端審問等の人間が持つ残酷さを目の当たりに見て、体内に溜まったヨゴレを描くという形で外に出して浄化したんだろうなぁ… 天才は努力の上に成り立つ、を体現した画家だと思う。2025/02/11
かなずちラッコ
2
勝手に想像していた印象とは違ってすごく真っ当な生き方でした。この本を読む限りは好印象しかない。2022/01/16
しゅうこう
2
かつて美術展に行った際、上品で静的な絵画が立ち並ぶ中「我が子を食うサトゥルヌス」を見た時の衝撃が忘れられない。もともと彩り豊かな絵を描いていたゴヤが晩年に黒い絵を描くようになった経緯を、当時の時代背景と、自身に起こった環境や身体的な変化に沿って解説してくれており分かり易かった。知れば知るほど沼にはまりそうな画家だ。2021/08/15