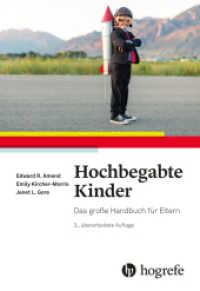出版社内容情報
茶道家から抹茶好きな一般まで、抹茶に関心を持つすべての人に贈る1冊。意外と知られていない“お抹茶”のことがまるごとわかる本
抹茶(碾茶:てんちゃ)は茶道にはなくてはならないもので、スイーツや飲料などにも広く使われ一般的にも人気となっていますが、抹茶についてその長い歴史や製法、効能などについて解説された類書(商業出版)は1冊もありません。抹茶関連の書籍はお菓子のレシピ本か、茶道、茶の湯でわずかに種類やお茶の点て方について解説したものだけです。唯一“お抹茶”の解説本としての本書では、“お抹茶とは何か”という定義から生産地、栽培、製造過程・加工法、南北朝時代から現代まで連綿と続く歴史、おいしい点て方、練り方、茶を飲み比べる趣向の遊び「闘茶」「茶講」、さらには茶用語の解説まで、抹茶について知られていない事柄をわかりやすく解説します。抹茶がもっとも身近にある茶道をたしなむ人から抹茶好きな一般の方まで――ぜひおすすめしたい、“お抹茶”がまるごとわかる1冊です。☆点て方で味に違いが出る、ひと缶1,000円の抹茶がおすすめ/抹茶を扱う市場は全国で一か所だけ?/飲んでおいしい抹茶の点て方(自分勝手流)/葉売りと挽売りの違いとは?/ハーゲンダッツショックって何? “お抹茶”発祥の地、京都宇治の抹茶問屋4代目が長年の研究を経て得た独自の視点から、詳しく解説します。
【著者紹介】
桑原 秀樹:早稲田大学政経学部卒業。24歳で(株)桑原善助商店代表取締役社長に就任。日本茶インストラクター制度では創設活動より参加。NPO法人日本茶インストラクター協会元副理事長長兼関西ブロック長。平成24年に、6年の歳月をかけて栄西の時代から現在までの抹茶の歴史を追いかけた『抹茶の歴史』を発刊、同作が第22回紫式部市民文化賞を受賞。日々、抹茶の製造に従事する傍ら、抹茶を一般家庭の暮らしに取り入れるべく、講演活動なども行っている。
内容説明
茶道家から抹茶好きな一般の方まで、抹茶に関心を持つすべての人に贈る1冊。意外と知られていない“お抹茶”のことがまるごとわかる本。
目次
第1章 抹茶の基本(抹茶とは何か?;抹茶の生産量と碾茶の生産量の不思議;「その他」という名前 ほか)
第2章 抹茶ができるまで(碾茶の品種解説;碾茶の栽培と製造;抹茶の製造工程 ほか)
第3章 京都における抹茶の歴史と推移(歴史1 抹茶の伝来・南北朝~室町時代;歴史2 茶道の隆盛・安土桃山時代;歴史3 武家の茶・江戸時代 ほか)
第4章 抹茶をおいしくいただく(抹茶の味と香り;抹茶のおいしい点て方;濃茶の練り方 ほか)
第5章 抹茶の成分と栄養素(抹茶は丸ごと成分を摂れる)
第6章 抹茶よもやま話(ハーゲンダッツショック;入札会場・入札・名札;商社・外観 ほか)
著者等紹介
桑原秀樹[クワバラヒデキ]
1949年京都府宇治郡東宇治町(現宇治市)生まれ。早稲田大学政経学部卒業。24歳で(株)桑原善助商店代表取締役社長に就任。日本茶インストラクター制度では創設活動より参加。NPO法人日本茶インストラクター協会元副理事長兼関西ブロック長。平成24年に、6年の歳月をかけて栄西の時代から現在までの抹茶の歴史を追いかけた『抹茶の研究』を発刊、同作が第22回紫式部市民文化賞を受賞。日々、抹茶の製造に従事する傍ら、抹茶を一般家庭の暮らしに取り入れるべく、講演活動なども行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tadashi_N
たかこ
こおり
散歩牛
てんちゃん
-
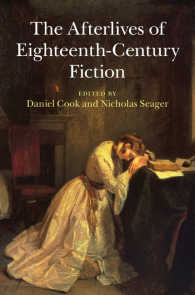
- 洋書電子書籍
-
18世紀小説と後世
The Af…