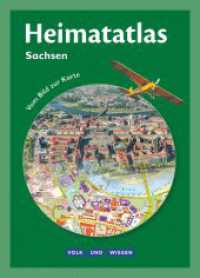出版社内容情報
弥生時代がぐっと身近になる一冊
弥生時代と聞いて、皆さんはどんなものを思い浮かべますか?
渡来人、稲作、絵柄のないつるりとした土器、環濠集落、卑弥呼と邪馬台国、続縄文文化に貝塚文化……
学校で習ってなんとなく聞いたことがある時代だからこそ、いろいろなものが思い浮かぶと思います。
では、実際のところ、弥生人たちはどのように日々を暮らしていたのでしょうか?
この本は研究から見えてきた弥生の姿を、小難しいことを抜きにしてザックリ知るための入門書です。
想像も交えながら、弥生時代の暮らしを見に行きましょう!
目次
彼らに会いに行く前に知っておきたい弥生知識
1章 社会の移り変わり
2章 衣食住とお仕事
3章 弥生時代の祭祀
4章 弥生遺跡ガイド
5章 続縄文時代と貝塚時代
6章 卑弥呼と邪馬台国の謎
著者等紹介
譽田亜紀子[コンダアキコ]
岐阜県生まれ。京都女子大学卒業。奈良県橿原市の観音寺本馬遺跡から出土した土偶との出会いをきっかけに、考古学に強く興味を持つ。各地の遺跡や博物館を訪ねて研究を重ねている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
美登利
86
縄文時代は話題にもなるし、興味がある人も多いと思うけど弥生時代はそうでもない。学校の授業でもサラッと流された気が。1番は稲作が広まったこととそのせいで人々が平等では無くなり争いが起こるようになったこと。卑弥呼のことは有名だが、未だに邪馬台国が特定されていないとか謎も多い。縄文と違うのはその時代の短さもあるけれど、文化の広がりのスピードは早かった。布を織り衣服を作り染めたり農具に鉄を付けたり様々な技術が広がった。現代に繋がる生活の源が生まれたように思う。北海道と沖縄には弥生時代が無いと言うのは知らなかった!2020/12/02
きみたけ
75
著者は歴史研究家の譽田亜紀子さん。奈良県橿原市の観音寺本馬遺跡から出土した土偶との出会いをきっかけに考古学に強く興味を持ち、各地の遺跡や博物館を訪ねて研究をされています。この本は、弥生人たちの日常生活について研究から見えてきた「弥生の姿」を知るための入門書です。弥生人は米だけでなく以外とグルメ。縄文時代は「狩りの友」だったイヌたちが、弥生時代はもっぱら「食材」に。 近所に「安満遺跡公園」が開園し、発掘のエピソードや弥生時代の紹介もあって面白かったです。大阪府立弥生文化博物館、機会があれば行ってみたいです。2021/11/05
ダミアン4号
62
(息)「おとーの考え方は古い!これからぁ“米”に決まってんべ!獲れるか獲れないかわかんないモンに頼ってっから飢えて死んじまうだよ…だから俺ぁヤツラと一緒に米作んだ…んで食うに困んない暮らしすんだ」(父)「そっか…確かにお前ぇの言う通りなんかもな知んねぃな…んでもな…米作ってそればっかに頼った暮らししてっどな米が不出来ん時ぃ村人同士で盗みっこになって争いになるって聞くぞ…俺にはそれが心配でなんねぃ」稲作が渡って来た頃、そんな会話があったかどうかはわかりませんが…気候が寒冷化、豊かだった自然の恵みが少なくなり2019/08/26
南北
60
弥生時代についてカラーのイラストや写真つきでわかりやすく解説されています。ただ、水田稲作が朝鮮半島から渡ってきたように書かれていますが、現在では長江中下流域から直接日本に伝わってきたことがわかっています。以前、国立科学博物館で「縄文VS弥生」という特別展があり、縄文人と弥生人の対比を強調していましたが、戦前と現在を比較しても平均身長の差異があるのは明らかなように必ずしも渡来人との混血を想定する必要はありません。また、養蚕が弥生時代から始まったという記述がなかったのも残念です。2020/10/11
えんちゃん
50
図書館新刊コーナーにて。イラストに惹かれて借りました。お米、戦争、土器。弥生人のルーツや顔つき身長まで。弥生ライフが楽しく図解されています。以前登呂遺跡のすぐそばに住んでいました。こんな生活が営まれていたとは。ロマンを感じます。卑弥呼の食事が豪華で驚き。2019/10/15