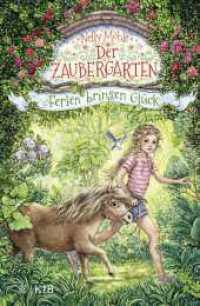内容説明
マスローは『動機と人格』をはじめ多くの著書、論文を出しているが、一貫してみられるのは、精神的に健康で自己を実現しつつある人間の研究である。とくに本書においては、これまでのかれの論ずるところを、もっとも総合的、集約的に要領よくまとめあげたもので、心理学者、教育者はいうまでもなく、その他人間科学を追求しつつある学究、あるいは実際に人間の問題ととりくんでいる人びとの一読に価するものとなっています。
目次
第1部 心理学領域の拡大(緒言健康の心理学へ;心理学が実存主義者から学び得るもの)
第2部 成長と動機(欠乏動機と成長動機;防衛と成長 ほか)
第3部 成長と認識(至高経験における生命の認識;激しい同一性の経験としての至高経験 ほか)
第4部 創造性(自己実現する人における創造性)
第5部 価値(心理学のデータと人間の価値;価値、成長、健康 ほか)
第6部 今後の課題(成長と自己実現の心理学に関する基本的命題)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koichiro Minematsu
40
マズローのいう「完全なる人間」とはどういう人間なの?っと純粋に知りたくて読みました。 ただ結果を求めている自分が恥ずかしくなった。 この一文がインパクトがあったからです。それは、「自己実現する人は、知らないもの、神秘的なもの、訳のわからないものにも平気で、積極的にひかれる」そう熱中するという力にこそ、完全に向かうものがあるのだと。2024/04/15
maimai
11
マズローの低次から高次へと生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、尊厳欲求、自己実現欲求へとあるみたいです。ある階層の欲求が満たされると人間は次の階層の欲求へと移るみたいです。マズローは承認欲求を否定しましたが、人がどう思うかよりも自分がどうしたいかの方が重要であるというのがこの欲求階層からみてとれます。私たちが生きていく上で真に大切なのは自分が心の底から望む願望をどう表現していくのかという点にあるとおもいます。自分の欲求が満たされている人は人に対しても優しくなれますし人間も形づくられるのだとおもいます。2015/06/10
デビっちん
9
人格は欲求の階層組織を中心に形成させられている。生理、安全といった基礎的欠乏欲求が満足させられたとき、はじめて順次に高次の成長欲求が階層的に出現する。そして、その安全性の感じ方は外部環境の提示ではなく、当人の内面的意識に左右される。自己成長に欠かせない認識の大部分は、具体と抽象が同時に行われる。世界をありのままに認知するというよりも、むしろ、自分の内面世界の構造を展望している。至高経験の瞬間には、認識の対象そのままとらえることができる。自己の内面世界を高めるために、美しいモノを見よう。2015/06/19
タケヒロ
8
「第三の心理学は、新しい人生哲学であり、新しい人間の概念である」「すなわち、ガリレオ、ダーウィン、アインシュタイン、フロイト、マルクスがおこなった意味での革命であり、そこでは、見たり考えたりすることの新しい方法、人間や社会の新しいイメージ、倫理や価値の新しい概念、運動すべき新しい方向性がみられる」との言葉が印象的。低次で強い安全欲求に打ち勝ち、高次の成長への欲求を強める方法は、認知的に「よく知り、よく理解する」ことにあるとのこと。あたりまえといえばそうだが、参考になった。2016/02/02
ざっく
7
5段階欲求のマズローの本。今年読んだ本の中で一番、いや、今まで読んだ本の中で一番面白かったかも。故に、理解できない部分があるのが悔しい。「成長の喜びと安全の不安が、成長の不安と安全の喜びより大きい場合に、成長をとげるのである。」とあり、低次の欠乏欲求が満たされない限り、高次の成長欲求には進めないとある。個人的には、低次の欠乏欲求は感謝で満たされ、高次の成長欲求は夢中になることで満たされるのではないかと感じた。しかし、「よい人間」とは何だろうか。感謝、夢中の次元では、良い悪いの次元を超えるような気もする。2021/04/28
-
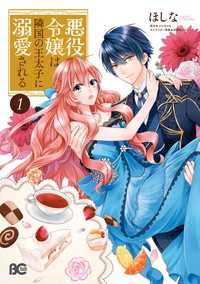
- 電子書籍
- 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される【タ…


![An Irish Policy for a Liberal Government. [with] Appendix](../images/goods/ar/work/imgdatag/12470/1247075516.JPG)