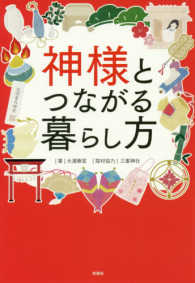- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 青春新書インテリジェンス
出版社内容情報
隅田川を船で旅立ち、奥州平泉から金沢を経て大垣に着くまでの476里・156日間、芭蕉は何を思い、そして何を伝えようとしたのか
生涯を旅に生きた俳人・松尾芭蕉にとって旅は人生そのもの。その代表作が『おくのほそ道』。隅田川を船で旅立ち、奥州平泉から金沢を経て大垣に着くまでの476里・156日間、芭蕉は何を思い、そして何を伝えようとしたのか。本書は『おくのほそ道』全行程とその世界観をふんだんな地図と図表で読み解きました。
【著者紹介】
1934年東京生まれ。61年早稲田大学大学院文学部研究科修了。現在、大東文化大学名誉教授。著書に『おくのほそ道』『芭蕉連句集』(岩波文庫)などがある。
内容説明
芭蕉はそこに何を見て、何を伝えようとしたのか!―いま甦る『おくのほそ道』の世界と人生観。
目次
序段 『おくのほそ道』を読む前に(松尾芭蕉の半生―旅立ち前の芭蕉の動向;芭蕉と『おくのほそ道』―新しみを追求した芭蕉の紀行文)
第1段 下野の旅―芭蕉庵から白河の関まで(序章―『おくのほそ道』の基調となる無常観;旅立―「第二の故郷」江戸との別れ ほか)
第2段 奥州をめぐる―須賀川から平泉まで(須賀川―奥州に入った芭蕉、俳壇の先輩と再会;あさか山・しのぶの里―「花かつみ」を訪ね巨石にしのぶ摺を想う ほか)
第3段 出羽路に跪を破る―尿前の関から象潟まで(尿前の関―中山越えの道、関守あやしむ;尾花沢―旧知の豪商、清風の手厚いもてなし ほか)
第4段 北陸路を行く―越後から大垣まで(越後路・一振―「荒海や」の名吟と遊女との出会い;那古の浦・金沢―対面を切望した俳人の死に慟哭 ほか)
著者等紹介
萩原恭男[ハギワラヤスオ]
1934年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、同大大学院文学研究科を経て、1976年より大東文化大学文学部教授に就任。現在は大東文化大学文学部名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。