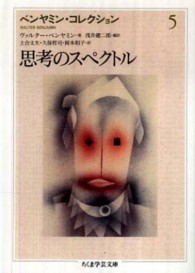内容説明
1903年から現在まで、東京の音楽文化を発信しつづける“レコード屋”の歴史をつぶさに追った、史上初のドキュメンタリー!東京のレコード店の歴史と実像とトリビアが満載!!
目次
序章
第1章 一九〇〇年~
第2章 一九二〇年代
第3章 一九三〇年代
第4章 一九七〇年代
第5章 一九七〇年代
第6章 一九八〇年代
第7章 一九九〇年代~
著者等紹介
若杉実[ワカスギミノル]
音楽ジャーナリスト。栃木県足利市出身。雑誌、書籍への寄稿をはじめCDのライナーノーツなどを執筆。CD、DVD企画も手がけ、これまで200タイトル以上送り出す。RADIO‐i(愛知国際放送)やShibuya‐FMなどラジオ番組のパーソナリティも担当していた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
阿部義彦
16
私はずっと仙台だったのでここに紹介されてるレコ屋には一度も行ってないけどレコードに関する思い入れたっぷりの物語に耳を傾けて歴史巡りをしました。「今40の人は50になっても音楽ソフトを買うでしょ。でも60が70になると買わなくなる。若い人なんかCD買ってないから。息子がいい例。ダウンロードばっかりだし、もっと言えばユーチューブ止まり。」今は中古CD屋レコ屋は実店舗を持たずにネットのみでの商売が主流。しかし、私に限らず音楽を聴くとそのアルバムをどの店でどうゆう感じで買ったかが蘇る事が有ります。これは性ですね。2016/04/17
qoop
5
通史として概括するのではなく、羅列された挿話群を通してその時代の音楽を消費文化の中で慈しむための一冊。80年代渋谷のレコードバブルを中心に編まれているのは、著者の主たる関心がそこにあると同時に、日本のレコード文化の分岐点だからだろう。CSV、WAVE(そして渋谷アールヴィヴァン)、宇田川町のタワーレコード… 僕はせいぜいそのくらいだけど。あの頃の情景を思い出すとともに当時は知る由もなかった事情を聞くと感心もし呆れもする。それにしても、CSVの営業期間がたった三年足らずだったなんて。2016/08/27
風花
5
かなり厚い本にも関わらず、読み出したら止まらずあっという間に読み終えてしまった。レコードやショップに関する様々な「初めて」の話から、音楽好きにはたまらないコアなエピソードまで、とにかく充実・満足の一冊。この本の中には、かつて六本木にあった細長く狭いビルの二階の、輸入レコードだけを取り扱っていた店に通いつめていた10代の頃の思い出が、そっくり詰まっていて胸が熱くなった。と同時に、人差し指一本で簡単に音楽を買えてしまう現在、その利便性と引き替えに失ったものが決して小さくないことにも気づかされた。2016/06/13
kawa
5
昔、レコード屋さん巡りが私の日常だったので懐かしく青春が蘇る気分。ジミー・ペイジが西新宿の店で、自分のブートレック(海賊盤)を回収していった話は笑えた(お店には気の毒ですが)。数は少なくなったが、今も老舗のレコード店が頑張っているようで何よりですね。そう言えば、5、6年前持っていた古い日本のロックのレコードの1枚に高額な値段がついていて(海外で人気らしい)、思わず売ってしまったことを思い出した。さっき、ネットオークションを見たら、それに15万円の値段がついていた(絶句!!)。ニッチな市場は健在ですね。2016/05/01
nizimasu
3
この本が刺さる人はDJだったり80年代に輸入盤を掘っていた人なんかは立ち寄ったことのある輸入盤屋さんや中古屋さんの名前が出てきてついほくそ笑んでしまうかもしれない。私も読んでいてそうでした。若杉さんはリミックスなんかの雑誌もやっていたから渋谷系から渋谷のレコード屋の喧噪も知る人物だけにあの頃の活気を感じさせてくれたし神保町界隈の古本屋の中にモザイクのように点在するレコード店にも注目していて関係者(中には故人も)取材している労作でもある。渋谷系という前作よりも引いたスタンスで懐かしく読める人も多いのでは2016/06/16
-
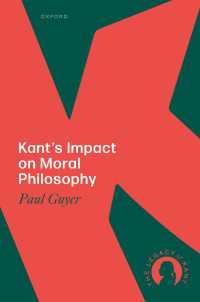
- 洋書電子書籍
-
カントの道徳哲学への影響
Kan…
-

- 電子書籍
- でびるち(4) GANMA!