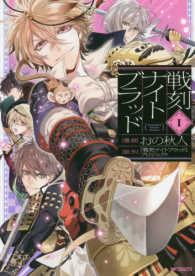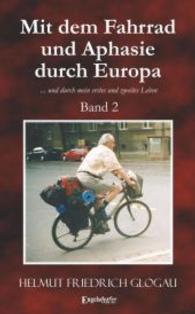内容説明
死にゆく他者を見守り支援するばかりだったこれまでの死生学を超え、人間最大の難問たる「一人称の死」を、哲学や人類学など人文学の知によって探究。高齢化社会で誰もが長い時間向きあわねばならない自らの死を徹底的に思索する。
目次
1 入門篇 人文死生学への招待(「死一般」ではなく「私の死」を謎として自覚するための実験実習;われわれは死を克服することが可能なのだろうか―「死への準備教育」と「スピリチュアルケア」への疑問;他界体験と仮想現実)
2 各論篇 死と他者の形而上学(“他者”とは時間を異にした“私”なのか―現象学で幼少期の体験を解明して遠望される死生観;ナーガールジュナから構想する生と死のメタフィジックス;自分の死としての非在―個体と可能世界;一人称の死―渡辺、重久、新山への批判)
著者等紹介
渡辺恒夫[ワタナベツネオ]
1946年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。東邦大学名誉教授。専門は、心理学・現象学
三浦俊彦[ミウラトシヒコ]
1959年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。東京大学文学部教授。専門は、美学・分析哲学
新山喜嗣[ニイヤマヨシツグ]
1957年生まれ。秋田大学医学部医学科卒。医学博士。秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻教授。専門は、臨床精神医学・精神病理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田中峰和
2
知ることができる死は、身近な他者の死(2人称の死)と距離のある他者の死(3人称の死)だけだ。自らの死は原理としては知り得ないが、「私」が死ぬこと(1人称の死)は共通の真理である。「私の死」の謎を、臨床的、医療的にではなく、徹底して形而上学的なアプローチで考え抜こうとするのが本書「人文死生学」の立場だ。哲学的、心理学的、現象学的、人類学的、宗教学的に5名の研究者が他者と自身の死の謎、「輪廻転生」に迫る。脳が機能を停止する直前に起こる臨死体験。睡眠を死の準備と捉えるなら、瞑想や念仏も死への接続になり得るのか。2018/03/16