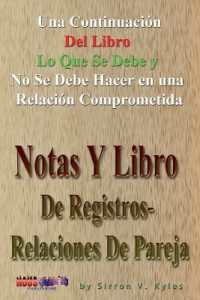出版社内容情報
だしを識り、だしを極めるための1冊。
日本料理にとって、だしは極めて重要な存在である。
どんな素材を使ってどうとるか?
本当に納得のいくだしをひくために大切なことは何なのか?
ただやみくもに探っていては、時間ばかりかかってしまい無駄も多い。大事なのは、多くのだしに触れると同時に、科学的な根拠に裏打ちされた「だしの仕組み」を知ることである。
そこで本書では、だしにこだわりをもつ東西7人の料理人に74のだしを、それを生かす料理とともにご紹介いただき、科学的なデータを元にした解説を加えた。
だしを根本的に理解するために役立つ1冊である。
目次
日本料理店7店の74のだしと料理/他ジャンルのシェフの和だし使い(日本料理晴山 山本晴彦;虎白 小泉瑚佑慈;多仁本 谷本征治;てのしま 林亮平;木山 木山義朗 ほか)
おもなだし素材(昆布/カツオ節/煮干し・焼き干し)
だしを考える(一番だしの調理科学(川崎寛也)
「だし」のサイエンスとデザイン(川崎寛也)
対談(川崎寛也/林亮平))
-
- 洋書
- Me Time
-

- 洋書電子書籍
- Proceedings of the …