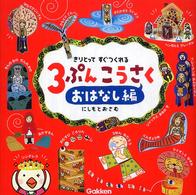内容説明
「いま必要なのは、もっと“遅い”インターネットだ」インターネットによって失った未来を、インターネットによって取り戻す。民主主義を半分諦めることで、守る。そのための「21世紀の共同幻想論」
目次
序章 オリンピック破壊計画(TOKYO2020;平成という「失敗したプロジェクト」 ほか)
第1章 民主主義を半分諦めることで、守る(2016年の「敗北」;「壁」としての民主主義 ほか)
第2章 拡張現実の時代(エンドゲームと歌舞伎町のピカチュウ;「他人の物語」から「自分の物語」へ ほか)
第3章 21世紀の共同幻想論(いま、吉本隆明を読み直す;21世紀の共同幻想論 ほか)
第4章 遅いインターネット(「遅いインターネット」宣言;「速度」をめぐって ほか)
著者等紹介
宇野常寛[ウノツネヒロ]
評論家。批評誌『PLANETS』編集長。1978年生。著書多数。立教大学社会学部兼任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
227
ついつい簡単に物事を断罪してしまうネット社会に問題提起した一冊。Ingress、ポケモンGOなど親しみやすい話も交えて書かれていたので、面白く読めた。2020/12/31
速読おやじ
51
民主主義の暴走によるポピュリズム回避のためには、立憲主義にパワーバランスを戻す方が良いという。世の中はグローバルなAnywhereな人とローカルなSomewhereな人に聞さんされている。虚構の時代は終わり、拡張現実へ移行し、ポケモンGOが生まれた。虚構(共同幻想)を共有することで人間は拠り所にしてきたが、インターネットの出現により、誰もが発信できるようになり、様々な幻想が溢れかえっている。Facebook(自己幻想)、LINE(対幻想)、Twitter(共同幻想)。遅いインターネットの概念にたどり着く。2021/01/14
ミライ
44
評論家の宇野常寛さんの新刊。平成の30年は「失敗したプロジェクト」、令和の時代になり日本の未来を取り戻すには「遅いインターネット(スロージャーナリズム的なネットでの質の高い情報発信)」が必要だと著者は語る、特に「書く」という行為についてじっくり考えさせられた。ディズニーのマーベル、NianticのポケモンGOを例に、「モノからコトへの時代の移行」を語っていたり、目の付け所が違うというか独特の視点で語られていて非常に面白い。人によってとらえ方がいろいろありそうな作品なので、読後感が分かれる一冊かなと思う。2020/03/07
T2y@
43
ギスギスした同調圧力高い、今のご時世で、タイムラインの空気を読み、流されるでも反論するだけでもなく、正しく「批評」する力。「書く」ことよりも先ずは「読解力」をと宇野氏は説く。改革に失敗したプロジェクトと定義された時代、平成から更に難儀で不明確な様相となった令和へ。『母性のディストピア』に閉じ籠らず、アップデートするキッカケとすべし。 2020/04/16
ころこ
38
走るというのは主体的だと書かれていますが、習慣化された「走り」に一旦乗ると、それはひたすら受動的な行為となります。この間違った比喩で、またもや環境管理型権力の設計をしていて、著者がどういった当否の審級でこういうことを語ろうと思うのか、いつも不思議に読んでいます。1章では無媒介に民主主義とかインターネットとか滔々と語っており、ある種の読者には心地よく、本を読み慣れていない読者には見取り図を示して読み易くなることは間違いありませんが、この気持ち悪さに反発する読者こそ社会を変えると、恐らく著者も分かっています。2020/02/27