出版社内容情報
日本人は、白黒をはっきりさせず、裁判沙汰になることを好まない。この遅れた法意識は、早晩法が法であるがゆえに従う「近代的な法意識」が当たり前のものとなることで、あらたまっていくだろう。各地の住民運動の盛り上がり方をみていると、川島武宜のこの「日本人の法意識」論の言う通りだと思えてくる。本書はこれに異を唱える。従来「遅れた法意識」だとされてきたものの中には、法が役立つがゆえに従うという「道具的な法意識」があるのではないか。この着想から、条文を含む多様な要因がからまりそのつど決まる秩序として法を描きだす。
【目次】
第1章 法と出会う
1 川島武宜の予言
2 法への道具的指向
3 法の動員
4 法の創出
第2章 法を創る
1 私たちは「空き缶条例」を見限った
2 条例制定過程
3 条例施行過程
4 条例をめぐる政治
5 法を創ることの困難
第3章 法を使う
1 利害対立と規制行政
2 紛争変容装置としての規制行政
3 マンション建設と開発規制
4 法を使うことの困難
第4章 法を語る
1 ローカルなルール形成と法制度
2 住民運動の発生と法へのアクセス
3 地域社会における自主的ルール形成
4 共同性の涵養と法の可能性
第5章 ローカルな法秩序
1 道具としての法
2 実現された法秩序
注
あとがき
索引
内容説明
創られ、使われ、語られることで、そのつど生産される複数の法秩序。道具として役に立つがゆえに法を動員する人々のさまざまな経験の分析を通じて、現代社会において法が果たす役割を考察する。
目次
第1章 法と出会う(川島武宜の予言;法への道具的指向 ほか)
第2章 法を創る(私たちは「空き缶条例」を見限った;条例制定過程 ほか)
第3章 法を使う(利害対立と規制行政;紛争変容装置としての規制行政 ほか)
第4章 法を語る(ローカルなルール形成と法制度;住民運動の発生と法へのアクセス ほか)
第5章 ローカルな法秩序(道具としての法;実現された法秩序)
著者等紹介
阿部昌樹[アベマサキ]
1959年群馬県に生まれる。1989年京都大学大学院法学研究科博士課程中途退学。現在、大阪市立大学法学部教授(法社会学)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
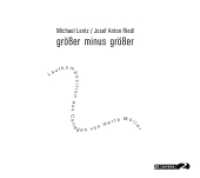
- 洋書
- größer m…





