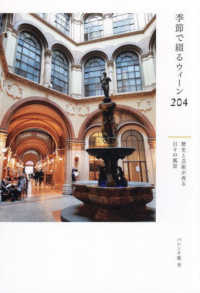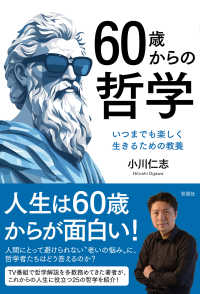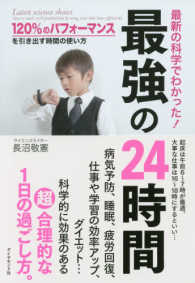出版社内容情報
1954(昭和29)年3月、ビキニ環礁で、一隻のカツオ漁船が水爆実験にまきこまれました。世界で初めて水爆の被害を受け、数奇な運命をたどった第五福竜丸のドラマチックな一生を描きます。
内容説明
ぼくの名まえは第五福竜丸。カツオや、マグロをとるためにつくれられた漁船だ。なんども、日本一の漁をした。そして…、1954年3月1日―。ぼくは太平洋のビキニ環礁で、水爆実験にあう。そこで体じゅうに死の灰をあびた。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
89
読友さんのレビューで知った絵本です。 ビキニ環礁で水爆実験に巻き込まれたあの第五福竜丸の数奇な運命を、船(第五福竜丸)の目線で描いた、迫力ある木版画による絵本です。ビキニから戻ってきた第5福竜丸は、改装されて東京水産大学の練習船として働き、その後廃船なってゴミの島に放置されました。船員だけではなく第五福竜丸自体も時代の犠牲者なんだと思います。水爆の恐ろしさを知るとともに、時代の流れも学ぶ必要がありますね。廃船となった後に放置されたゴミの島が今は夢の島への様変わりしていることも時代の流れの一つですね。2025/08/26
ベーグルグル (感想、本登録のみ)
46
名前ぐらいしか知らなかったし、第五福竜丸を守ろうと動いた方々がいた事で今に至る事に感謝したい。1954年3月1日、南太平洋上のビキニ環礁。アメリカの水爆実験で被曝した、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」について、船目線で書かれている。木版画の絵が素晴らしい。読んだ日の池上彰さんのテレビで第五福竜丸の話題があり、より学びが深まった気がする。読み継がれて欲しいし、いつか展示館も観に行きたい。2025/08/16
ヒラP@ehon.gohon
22
第5福竜丸は日本に戻ってから、東京水産大学の練習船となり姿を変えた後廃船となって、ゴミの島に放置されていた。 展示館いっぱいに存在している船よりも、様々な展示品や解説パネルに関心が強かった。 しかし、死んだ人はそこにはいないけれど船はそこにいる。 船も時代の犠牲者だと思ったら、この絵本もとても大事な物に思えてきた。 木版画で骨太の絵本。 漁船としてのホコリを持ったように思える絵本です。 第5福竜丸の数奇な運命とともに、子どもたちに伝えたいメッセージがいっぱい詰まった絵本です。2010/11/13
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
21
見返し部の「ぼくの名まえはは第五福竜丸」、これで一気に引き込まれました。船に関わった人たちが背負わされた理不尽さ、それを「ぼく」が一手に引き受けてくれたかのような。そして日本の造船技術の素晴らしさ。マグロ船といえば過酷なものの代名詞のようになっているけれど、そこまでしてマグロを食べなきゃいけないのかと思わされました。水爆実験は愚行でしかなかった。無人地区であれば被害はないと思ったのか。愚行を繰り返さないためにも史実の記録を残すことは必須。第五福竜丸のことを知らない方にぜひ読んでいただきたいです。2025/07/01
Cinejazz
21
1954年3月1日、南太平洋上のビキニ環礁。アメリカの水爆実験(広島原爆の1000倍の破壊力をもつ)で被曝した、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」。その100トンを超える漁船の数奇な運命を、画家<赤坂三好>氏の切迫感のある画筆で、誕生から展示館で保存されるまでの生々しい歴史が描かれた、親子で読む真実の物語。2025/03/03