内容説明
一人一人の学習者が、対話をする喜びを存分に感得しつつ、自己の資質・能力を事実として伸長させる「対話型授業」を、どう実現するか。「深い思考を生起させる対話型授業の実践のための12の要件」を紹介しつつ説き明かす。
目次
第1部 理論編―対話型授業とは(対話・対話型授業;深い思考力;学びの構造)
第2部 実践編―深い思考を生起させる対話型授業の実践のための12の要件(対話の活性化のための物的・人的な受容的雰囲気づくり;多様な意見・感覚・体験を持つ他者との対話機会の意図的設定;差違性の尊重、対立や異見の活用による思考の深まりや視野の広がり;自己内対話と他者との対話の往還による思考や視野の広がり;沈黙の時間の確保や、混沌・混乱の活用による思考の深化 ほか)
著者等紹介
多田孝志[タダタカシ]
金沢学院大学文学部教育学科教授、博士(学校教育学)。目白大学人間学部児童教育学科教授、青山学院女子短期大学、立教大学大学院、東京大学教育学部、学習院大学文学部兼任講師歴任、日本学校教育学会元会長・常任理事、日本国際理解教育学会元会長・顧問、異文化間教育学会名誉会員、日本グローバル教育学会常任理事、共創型対話学習研究所所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
にくきゅー
2
筆者が言っていることと、少しズレるけども、グループワークのときの沈黙を価値づけてもよいなぁと思った。わいわい、がやがやしているだけがよいのではなくて、一回立ち止まってじっくり考えるのも大事だよ、ってことを教師側が価値づけることは大切な気がする。2020/03/15
笛の人
1
今回は小説ではなく実用書を読みました。 かなり前から少しずつ読み進めていたのですが、やっと読み終わりました。タイトルからもわかる通り、理論と実践を12個の点から書かれていました。 これがとてもわかりやすかったです。印象に残ったことはたくさんあるのですが、沈黙の活用、物語の創作、思考を発展させるための具体的な話型が特に印象に残りました。辞書的な使い方もしやすそうなので、色々な場面に活用していきたいなと思いました。2022/06/26
シモン
0
ちょっと危ないこと、やってはいけないことをするときに学習意欲が高まるというのが印象的だった。子どもに挑戦させるというのは、必ず成功することだけをさせるのではなく、失敗するかもしれないことでもさせてみることだと思う。ちょっと危ない、やってはいけないけどと分かっているけどやってみたいことに挑戦して失敗することも新たな学びで、大人になってから挑戦するときに危険を予測して行動する力につながるように思う。もちろん、大きな危険にならないような教師の支援は必要2025/01/07
-
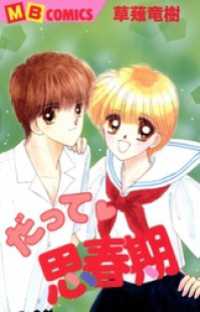
- 電子書籍
- だって・思春期01 MBコミックス
-

- 和書
- 危険な椅子 角川文庫




