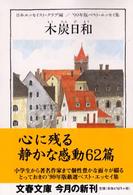出版社内容情報
『愛するということ』(改訳・新装版)はこちら。
愛は技術であり、学ぶことができる――
私たち現代人は、愛に渇えつつも、現実にはエネルギーの大半を、成功、威信、金、権力といった目標のために費やし、愛する技術を学ぼうとはしない。
愛とは、孤独な人間が孤独を癒そうとする営みであり、愛こそが現実の社会生活の中で、より幸福に生きるための最高の技術である。
◆各界の方々からのメッセージ
杏(モデル・女優)
「愛」を、学術的に学ぶ本。
解剖・分解され、構築される愛のメソッド。
本能として持ち合わせた愛を、いったいどれだけ言葉で表せるのだろう。
愛されるのではなく、愛する技術とは? 生きるためのヒントがつまっている。
岩井志麻子(作家)
とても簡単なことが、大いに楽しめ学べる複雑なドラマとして描かれています。とても難しいことが、誰にでもわかるやさしい言葉で表されています。
岡崎武志(書評家)
現代は「愛」が消費材のように叩き売られる時代。半世紀も前にフロムは、「愛」は「幸福に生きるための最高の技術」と断言。その修練のために「信じる」ことの必要性を説いた。かくも「愛」は困難だ。
姜尚中(東京大学教授)
愛に飢えながら、愛を語りえないわたしたちの不幸。それは、愛が歪んだナルシシズムと利己心の別名になっているからだ。愛するということは、自己への信頼と他人の可能性への信頼にもとづく最も人間らしい技術にほかならないことを知ったとき、愛は輝きを増し、そしてわたしの希望となった。本書によってわたしは救われたのだ。
菊地成孔(音楽家・文筆家)
「愛ってこんなに面倒くさいものなの?」と思うでしょうけれども、こんなに面倒くさいんです。あらゆる愛の実践が、歌の歌詞だけになってしまった現代に残された、今となっては喰えないぐらいにキツイ本です。「ずっとそばにいるよ」とか「声聞けないと死にそうだよ」とかいった言葉に本気でグッと来るような人は、読まない方が良いかもしれません。
小谷野敦(比較文学者・作家)
間違えてはいけない。これは「愛されるということ」ではない。この本をいくらよく読んで何かを実行しても、好きな相手から好かれるようにはならない。そういう勘違いさえしなければ、読んでもよい。
辛酸なめ子(漫画家・コラムニスト)
愛に迷った時、求めても得られなくて絶望にかられた時、この本の愛についての理性みなぎる文章に触れるとたちまち精神が鎮静化します。
鈴木謙介(社会学者・関西学院大学助教)
本書の冒頭でフロム自身が言うように、私たちは「愛される技術」についてはいつも考えているけれど、「愛すること」は難しいことではないと思っている。だが実際には、相手をひとつの人格として尊重し、愛するのは、とても難しい。愛されたいと思う人こそ読むべき一冊。
谷川俊太郎
『愛するということ』を、若いころは観念的にしか読んでいなかった。再読してフロムの言葉が大変具体的に胸に響いてくるのに驚いた。読む者の人生経験が深まるにつれて、この本は真価を発揮すると思う。
土井英司(「ビジネスブックマラソン」編集長)
人を動かす秘訣を学びたいなら、100冊のマネジメント本を読むより、このフロムの名著を読むといい。たった一つの原則――愛とは対象の問題ではなく、愛する能力の問題である――を知るだけで、うまくいくはずだ。
夏木マリ(ミュージシャン・ディレクター)
いくつになっても愛についてのメカニズムに答えはないと思っていた。著者は「愛は技術だ」と言い切る。人を愛する技術。そういえば、こんな私も…、人を愛して隣人に優しくなれたような気もしている。そんな時、自己成長を体感しているような気もしている。
「人を愛することは自分を知ること」 この本が明解に導いてくれた。
新浪剛史(ローソン社長)
本当の愛とは何かを考えれば、
人生も、真に企業が歩むべき道も見えてくるのだと思います。
西村佳哲(リビングワールド代表、働き方研究家)
人が人生を通じて触れつづけていたいものは愛、と語る言葉に時々出会う。そうかもしれないと思うし、あまりに大事な話で、言葉にしたくないとも思う。この本はそれを言葉にしているわけですが、生涯を通じて何度も読み返したい。そんな一冊です。
日野原重明(聖路加国際病院理事長・名誉院長)
私は本書を読み、「技術を習得する過程として、1.理論に精通すること、2.習練に励むこと、3.その技術を習得することが究極の関心事にならなければならない」という言葉に接し、これが医学にも音楽にも通じることに気づき、強い感動を覚え、臨床医や看護・介護職の方々にこの本を読むことを勧めている。
松浦弥太郎(『暮しの手帖』編集長)
愛とは、自然と涙が流れること。愛するとは、すべてを信じることから学ぶ、工夫と発案に満ちた無償の生き方である。本書は現代人が欲望と引き換えに失った、人間らしさに立ち返るヒントに満ちた一冊といえよう。
宮台真司(社会学者)
愛とは、
愛される〈体験〉ではなく、
恋に落ちる〈体験〉でさえもなく、
喜びを与える〈行為〉たるがゆえに、
磨かれるべき「技術」を要するという本書は、
何度読んでも、そう、そうだったはずだとの気付きをもたらす。
森まゆみ(作家)
初読の学生時代、私はカップルの片われで、「愛されること」ばかり考えていた。55歳のいま、結婚、出産、育児、離婚、市民運動、更年期障害、老いの自覚を経て再読し、この本が何百倍も広く深い、生きる意味を照らす鏡であると思えてきた。
山田太一(脚本家)
出回っている陳腐な愛で諦めている人に、修練を積めば、もっとましな愛、ましな人生、ましな世界を手にすることが出来るのではないか、といっている本です。
◆エーリッヒ・フロム
「新フロイト派」の代表的存在であり、真に人間的な生活を可能とする社会的条件を終生にわたって追求したヒューマニストとしても有名。著作に『自由からの逃走』ほか多数。
内容説明
人間砂漠といわれる現代にあり、〈愛〉こそが、われわれに最も貴重なオアシスだとして、その理論と実践の習得をすすめた本書は、フロムの代表作として、世界的ベストセラーの一つである。
目次
第1章 愛は技術か
第2章 愛の理論(愛、それは人間の実存の問題にたいする答え;親子の愛;愛の対象)
第3章 愛と現代西洋社会におけるその崩壊
第4章 愛の習練
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
ひろちゃん
mukimi
青蓮
Cambel
-

- 電子書籍
- 論文的思考によるフラット話法!立場も主…
-
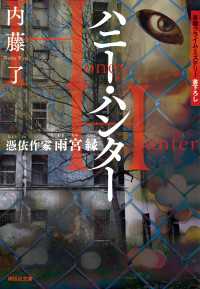
- 電子書籍
- ハニー・ハンター 憑依作家 雨宮縁 祥…