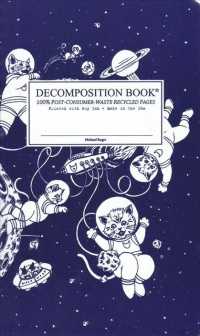出版社内容情報
ロシアの壮大な歴史をコンパクトに知ることができる永久保存版。緊迫するウクライナ情勢の解説も。
【著者紹介】
1944年生まれ。一橋大学経済学部卒業。北海道大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。北海道大学大学院文学研究科教授を経て、現在、北海道大学名誉教授。専門はロシア中近世史。著書に 『タタールのくびき』など多数。
内容説明
なぜ、革命はおきたのか?強権による専制はどうして必要だったのか?近くて遠い国、ロシアの真実。
目次
ロシアという国
キエフ・ロシア(キエフ大公国)―ロシア史の揺籃時代
「タタールのくびき」―モンゴル支配下のロシア
モスクワ大公国―ユーラシア帝国への道
近代ロシア帝国(貴族と農奴のロシア;苦悩するロシア)
ソヴィエト・ロシア―社会主義をめざすロシア
ペレストロイカからロシア連邦へ―今日のロシア
著者等紹介
栗生沢猛夫[クリウザワタケオ]
1944年、岩手県に生まれる。1967年、一橋大学経済学部卒業。1974年、北海道大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。小樽商科大学教授、北海道大学大学院文学研究科教授を経て、北海道大学名誉教授。専門はロシア中近世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。