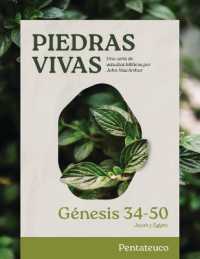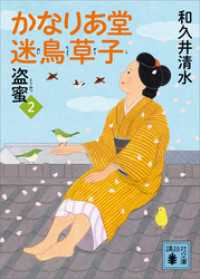出版社内容情報
短歌とビジネス文書の言葉は何が違う? 共感してもらうためには? いい短歌は社会の網の目の外にある。穂村弘のやさしい短歌入門。
穂村 弘[ホムラ ヒロシ]
1962年、札幌市生まれ。歌人。歌集に、『シンジケート』『手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)』他。エッセイ集他に、『世界音痴』『現実入門』他。また、絵本翻訳も多数。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
岡部敬史/おかべたかし
124
穂村弘さん。いいですよねぇ。この本は、いろんな短歌を紹介し、時には「改悪例」も示しながら「よい短歌とは?」を示してくれる。要は「わかりやすさ」「合理性」と対局のところに「短歌の良さ」があるということ。人は落語もそうだけど、そういったちょっと外れたところにあるものに面白さやユーモアを感じるわけで、こういった気持ちは社会として大切にしたいなーと思った次第。短歌、やるのに勉強するってのもちがうのだろうからすっとやってみたい、なと思う2021/06/06
mukimi
104
社会的に価値のないもの、換金できないもの、名前のないもの、しょうもないもの、弱いもの、へんなものの方がいい、短歌においては。という一文に救われた(先日彼氏に(感性が)ヘン、と言われてざっくり傷ついたから。因みに自覚もある)。このヘンな感性を大切にしてやろうと思えたし短歌やってみたくなった。(感性に忠実に)生きることvs(社会的秩序を守り)生きのびることの対比もすごい面白くて、仕事に時間と体力の95%を捧げてる私としては後者で精一杯なんだけど、前者にかける比重も大きくして自分らしさを凍らせたくないと思う。2020/08/02
吉田あや
97
短歌のルールや、”短歌とは”といった形式ばったものではなく、短歌という角度で世界を捉え、柔らかな発想へ導く脳みそのストレッチのような本書。欠点に見る日常の愛おしさ、一見なんでもない景色にふと時の流れを想う、ノスタルジーの暴力的なまでの感傷性。カメラの立ち位置、思考の転換で詩の宿る場所は其処此処に見えてくる。短歌にみる生きることの余地と、短歌を「詠み」「読む」ことで生まれる共感と妙の愉しみ。息苦しく思う日は、短歌で心に伸びやかな世界のくびれを描きたい。2019/03/25
masa
92
テスト前、「全然勉強してないわ」と目の下にクマをつくりながらアピールする。そういう輩にだけはなるまいと心に誓った。みんなで短歌を詠む前にこれを読んで黙っていたらそれを破ることになるから、レビューするしかあるまい。短歌では社会的に無価値で換金できない方が輝く。おかんの腕に輪ゴム、陰毛みたいなパーマ、ヒョウ柄の服、DVDはビデオでTVゲームはファミコンでリモコンはピコピコ呼び、全部憎んでいた筈なのに、今ではいいぞ、もっとやれ!と思ってる。ね、もしかしてそんな気持ちわかりますか?穂村さんにそう聞いてみたくなる。2019/12/20
あきら
78
「生きのびる」と「生きる」 「替えのきく生き方」と「替えのきかない生き方」。 とても救いなのは、それは二者択一ではないこと。 改悪例を提示していく構成も斬新で、勉強になった。 これは短歌入門の枠を超えた、ビジネス書みたいなものだと思った。2021/05/30