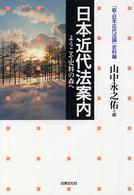内容説明
9・11テロは我々の内なる欲望を映し出す鏡だった―あの破局をもたらした根源的要因をさぐり、資本主義社会の閉塞を突破して奇跡的に到来する「共存」への道筋を示してみせた画期的論考。逆説に満ちた、スリリングな展開は大澤社会学の真骨頂。10年をへだてた2つの「11」から新たな思想的教訓を引き出す3・11論を増補。
目次
序章 9・11テロ、そして社会哲学の失効
第1章 文明の内的かつ外的な衝突
第2章 イスラームと資本主義
第3章 原理主義的転回
第4章 弱くかつ強い他者たちへ
補章 倫理の偶有的な基礎―9・11と3・11の教訓
著者等紹介
大澤真幸[オオサワマサチ]
1958年、長野県生まれ。社会学者。思想誌『THINKING 「O」』主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
42
2013.02.21(初読)大澤真幸著。 (刊行) 『文明の内なる衝突』(NHKブックス、2002.06)増補版です。 (カバー) 9.11テロは、我々の内なる欲望を映し出す鏡だった。 あの破局をもたらした極限的な要因を探り出し、資本主義社会の閉塞を突破し、奇跡的に到来する「共存」への道を示す「画期的論考」。 逆説に満ちたスリリングな展開-大澤社会学の真骨頂。 10年を隔てた二つの「11」から、新たな思想的教訓を引き出す3.11論を増補。 2013/02/21
i-miya
38
2013.02.21-2(初読)大澤真幸著。 2013.02.19-2 (参考文献、つづき) +中沢新一。 +中村哲。 +マルティン・ハイデガー『パルメニデス』。 +サミュエル・反沈トン、ハンチントン。 ミシェル・フーコー。 +ヴァルター・ベンヤミン『暴力批判論』。 +カール・マルクス。 サルマン・ラシュディー。 (あとがき) 本書は、9.11テロの衝撃のもとで書かれた。 書いておかないと、忘れてしまう。言葉にして残しておくべきだ。 2013/02/21
i-miya
37
2013.02.22(つづき)大澤真幸著。 2013.02.20 ①至高の規範を直接与える。 ナショナリストや、kミュニタリアン、宗教的原理主義者など。 ②実質的な規範を与えることを断念し、主として普遍的に妥当する規範-正義-を構成するための形式的な手続きを定式化すること。 ジョン・ロールズ。 2013/02/22
i-miya
36
2013.02.27(つづき)大澤真幸著。 2013.02.26 (◎社会哲学の無力、つづき) テロリストは、例外的少数者ではなく、共感したり、心理的に共感するものを入れると、億単位にのぼる。 ①のコミュニタリアンやナショナリストは、この数千人の無辜の同朋を死に追いやったテロリストたちに対する戦いを、つまり戦争を支持する。 ②にとって、テロリストは、その行為は、想定外の行動となる。 ②にとって、テロリストは、理論上存在するはずのない人々となる。 対応は戦争しかない。 2013/02/27
ころこ
35
序章にあるコミュニアリアニズム、リベラリズム、ポストモダン・多文化主義の三幅対の説明が素晴らしい。多文化主義からコミュニアリアニズムに回帰しているのがローティであるというので、しばらく本を読むのを止めて考えさせられました。多文化主義のメタ価値は多様性という単一性であるという指摘は鋭いです。文明の内なる敵を見つめてみると、冒頭の三幅対のリベラリズムと違った〈リベラリズム〉が浮上することになります。著者は9.11に端を発した具体的問題よりも、資本主義の展開が原理主義の挑戦を招き寄せるのはなぜか、という抽象的問2019/11/21