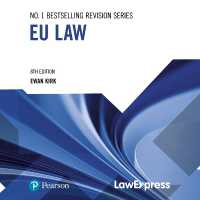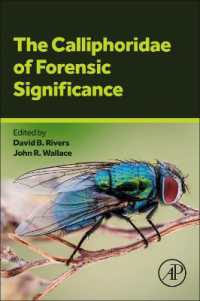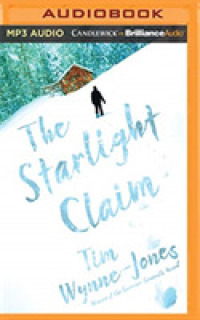感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nbhd
12
1975年の本。要約すると(1)行政システムや大建築家がマスタープランをつくってしまうと、利用者の使い勝手や居心地のよさが軽視されてしまう。(2)なので、つくる側と利用する側で代表委員会をつくって、(3)最初から予算めい一杯の完成プランをつくるのでなく、改修も見込んで10年ペースで段階的に良いものにしましょう。(4)委員会にあたっては、建築家が「こんなときには、こんな方法」という“パターン”を用意するので、意見をつのって、(5)パターンどうしがかち合ってしまったときは、うまいこと調整しましょう。2017/09/07
roughfractus02
7
建築はトップダウンから建築物や交通インフラだけでは自生的なコミュニティは形成されない。著者は建築物を建てる者と住む者が参加して個々の経験や個性を有機的に協働させるプロセスと捉え、自生的ゆえに徐々に形成されるとした。1960年代、学生運動の中、学生たちのコミュニティ形成を重視したパタン・ランゲージを組み立てて誰もが参加できる場に大学建築を変えようとする。本書は、包括的パタンと個別で詳細なパタンを選分けつつ組み立て、そのつど有機的か診断して修正・調整しながら現実的問題と擦り合わせていく漸進的な試行錯誤を記す。2025/06/30
鵐窟庵
7
本書は1960年代における建築と都市の設計の実験書である。アレグザンダーは当時有効な設計方法を見出そうとしていた。市民や利用者の参加型の設計、スケールによって異なる部分と全体の設計プロセス、生産コストと漸進的な事後設計、集団の種類ごとのパターンランゲージ、など現代のまちづくりやワークショップや建築設計に通じる、最初期の思想や理論が窺える。徐々に時間をかけて、都市スケールの建築を設計するという、漸進的な設計のあり方は現代の日本の建築の状況において、内装やリノベーションにおいて有効な指針を与えてくれるだろう。2019/02/12
Nanako Kono
0
(イタリア旅行中) 結構建物の見方が変わる。ヴェネチアの建物の秩序。。2014/03/25