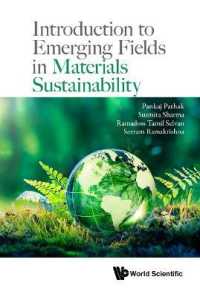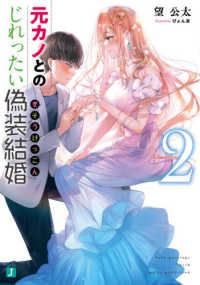目次
情けある昔の人は
春きぬと思ひなしぬる
いとまなく柳の末に
春や何ぞきこゆる音は
枝もなく咲き重なれる
かすみくもり入りぬとみつる
花の上の暮れゆく空に
風はやみ雲のひとむら
すずみつるあまたの宿も
照りくらし土さへ裂くる〔ほか〕
著者等紹介
阿尾あすか[アオアスカ]
1978年奈良県生。奈良女子大学卒業、京都大学大学院博士課程修了。現在、国文学研究資料館特定研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。