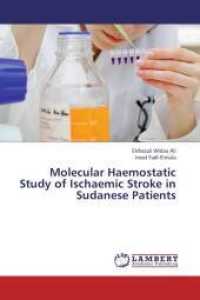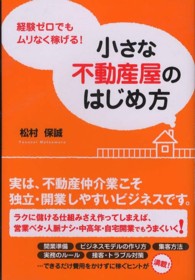内容説明
大衆文化とカウンターカルチャーのビート世代最大の詩人、アレン・ギンズバーグの本質を検証し、彼の文学的価値を解明する本邦初の著作。
目次
第1章 「吠える」(“Howl,”1956)―預言者的詩人としてのギンズバーグ(ビート詩人が「豊かなアメリカ」の奥底に見たもの;正気と狂気を逆転させた「ヒップスター」たち ほか)
第2章 「カディッシュ」(“Kaddish,”1961)―解体された葬送悲歌(伝統的なエレジー;反エレジーとしてのネィオミ像)
第3章 『アメリカの没落』(The Fall of America,1972)―「渦」の旅(「渦」のエネルギー;アメリカの没落)
第4章 ギンズバーグのリズム―「息」の詩人(ギンズバーグの長息詩行;「息」のエネルギー)
著者等紹介
谷岡知美[タニオカトモミ]
広島市生まれ。広島女学院大学文学部卒業。同大学大学院言語文化研究科博士後期課程修了。博士(文学)。広島女学院大学総合研究所特別専任研究員を経て、2011年4月から広島修道大学人間環境学部准教授。専門は英米文学、ビート世代の文学・文化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
17
著者はギンズバーグが次世代のボブ・ディランらに影響を与えたビート詩人としてのギンズバーグに注目する。それは同世代の仲間に語る(ケルアックやニール・キャサディ)等身大の語り口(上から目線ではない)、そこに一行の息で一気に語る手法を生み出していく。ただギンズバーグは同時にホイットマンの壮大な詩からも影響を受けていた。『吠える」で圧倒的な若者の支持をうけたのはそういうことだった。さらに『カディッシ』では精神病を患った母のドラマをエレジーで語るなど伝道師の一面もあった。そこに私小説的なものを社会性へ繋げる。2024/08/21
ぴらるく
0
最初のビートの解説わかりやすかった。狂気は正気。正気は狂気。吠えよう。2015/12/09
サトル
0
ザ・ヒッピーの流れで読んでみたが、アレン・ギンズバーグの人物評伝ではないから、そして余りにも彼の詩の世界に特化しているものだから、速足で飛ばし読みするしかなかったけれど、ビート・ジェネレーションのビートたるものは分かったような気がする。打ち負かされ疲れ果てた者たち、天使の頭をしたヒップスターたち。hipsterって流行に敏感でサブカルチャー好きの若者を指す言葉らしい。当時の社会状況をギンズバーグは「吠える」で詩を書いたのではなく”息”をしたのだと云う。結局のところ、なぜヒッピー登場となったかは分からない。2023/09/11
-

- 電子書籍
- 女性マネージャーの働き方改革2.0 生…
-
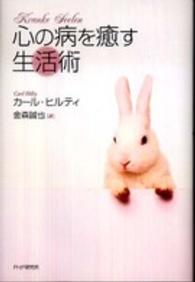
- 和書
- 心の病を癒す生活術