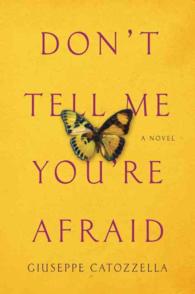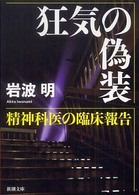出版社内容情報
羽釜や洗濯板など、明治~昭和時代にはつかわれていたけれども、しだいに電気製品に代わられたものを中心に、少し昔の生活道具を紹介
あの「昔のくらしの道具事典」がグレードアップ!
羽釜や洗濯板など、明治~昭和時代には使われていたけれども、
しだいに電気製品に代わられたものを中心に、少し昔の生活道具を紹介。
大きな写真で見やすく、つかい方、進化の様子、マメ知識などのコラムも充実。
大人にはなつかしい、子供には興味深い、道具の数々。
調べ学習にはもちろん、世代間の話題作りに最適です。
ロングセラーの「昔のくらしの道具事典」を、ページを増やし、オールカラーにしてリニューアル。さらにグレードアップして、使いやすさそのまま。
【著者紹介】
【小林 克・監修】 1959年新潟県生まれ。日本大学大学院修士課程終了。考古学、物質文化研究の視点で、近世から近代の生活文化を研究している。1989年より江戸東京博物館の開設準備に携わり、現在は江戸東京博物館分館江戸東京たてもの園学芸員。日本大学芸術学部、同文理学部非常勤講師。
内容説明
人は、昔からさまざまな道具をつかってくらしてきました。くらしをべんりに豊かにするために、道具にはいろいろな工夫がされ、いまでは、スイッチひとつで動く機械もたくさんあります。この本では明治、大正、昭和につかわれていたくらしの道具を紹介しています。いまでもつかわれている道具もあります。もうほとんどつかわれなくなった道具もあります。ぜひ、おとうさんおかあさんやおじいさんおばあさんといっしょにページをめくってみてください。昔のなつかしい思い出を話していただけるかもしれませんよ。
目次
第1章 台所の道具
第2章 食卓の道具―いろりのまわり
第3章 水まわりの道具―お風呂、トイレ、洗濯
第4章 住まいの道具
第5章 夏の道具、冬の道具
第6章 仕事の道具
著者等紹介
小林克[コバヤシカツ]
1959年新潟県生まれ。日本大学大学院修士課程修了。考古学、物質文化研究の視点で、近世から近代の生活文化を研究している。1989年より江戸東京博物館の開設準備に携わり、現在は江戸東京博物館分館江戸東京たてもの園学芸員。日本大学芸術学部、同文理学部非常勤講師
神野善治[カミノヨシハル]
1949年東京都生まれ。伊豆の海で民俗資料館の学芸員を12年、文化庁の調査官として民俗文化財の保護活動10年、現在、武蔵野美術大学教授。博士(民俗学)。民俗技術、人形の民俗などを追求(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。