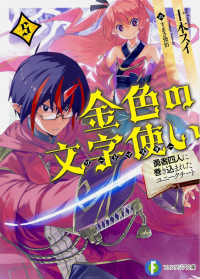内容説明
関白・道隆が亡くなり、権力は道長へ移り、強力な後ろ楯を失った中宮定子。兄・伊周と弟・隆家に左遷流刑宣告が下り、後宮には次々と新しい女御が入内、一族は衰退の一途をたどる。定子に仕える海松子は、定子の美しさと人生の光耀、世のときめきだけを書きとどめ、「春はあけぼの草子」をついに完成させる。
著者等紹介
田辺聖子[タナベセイコ]
1928年大阪生まれ。樟蔭女子専門学校国文科卒。64年「感傷旅行(センチメンタル・ジャーニイ)」で芥川賞受賞。軽妙洒脱でユーモラスな小説を主体に歴史エッセイ、評論など幅広く活躍。87年「花衣ぬぐやまつわる…わが愛の杉田久女」で女流文学賞、93年「ひねくれ一茶」で吉川英治文学賞、94年菊池寛賞受賞。95年紫綬褒章受章。98年「道頓堀の雨に別れて以来なり」で泉鏡花文学賞、井原西鶴賞、99年読売文学賞受賞。2000年文化功労者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のびすけ
25
相思相愛の主上と中宮定子さまのなんと仲睦まじいこと。そして、定子さまの後宮のなんと賑やかで楽しそうなこと。それもこれも定子さまのお人柄ゆえなのですね。そんな定子さまと清少納言は心を通わせ、定子さまを想い書き綴った「春はあけぼの草子」。とても素敵で胸を打つ物語でした。清少納言や定子さまの人間性をユーモアも交えて細やかに丁寧に描いた田辺聖子さん、お見事でした。ただ上下巻あわせて1000頁、読了に10日。ちと長かった。2024/05/18
assam2005
21
後半は一気に道長の威光に負け、押しやられていく。少納言から見る中宮・定子像はどこまでも貴く清らかで美しいのだが、後半になり儚げな感じが加わる。自分の最期を予言していたかのように。そして男と肩を並べて生きる少納言は、現代における「おひとりさま」の先駆者だったのではないか。女が、男に振り回されることなく一人で生き抜けるのだと示した少納言。男女差別に関してはかなり先鋭的ではあるが、身分差別に関しては当時の一般的な意見。弱者の立場に立って、初めて見える人だったのだろう。弱者である女だから見えた世界。2020/11/03
コニコ@共楽
15
上巻であんなにも栄華を極めた定子一族が、道隆の死後、長徳の変、火事、道長の娘の彰子の入内と畳みかけて起こる事件で衰退していき、胸を打つ。そんな中、清少納言は一心に中宮定子に仕えお慕いし、”春はあけぼの草子”を美しく明るく綴る。『枕草子』の底に流れる悲しい中宮定子の物語がじわー染み入る。清少納言の心意気のある筆で書かれた『枕草子』は、後宮の素晴らしき人々が千年前にイキイキと生きていたことを教えてくれる。田辺聖子さんもまた平安の世界の生身の人間を見させてくれた。1000ページを超す長篇、堪能いたしました。2025/02/23
getsuki
13
下巻まで読了。清少納言と定子さまの細やかなやり取りは楽しくも、奥深い。それを引き立たせる男性陣の配置も上手いなぁと思うなど。深い知識と教養に裏付けられた文章に時々混じる現代語が、雰囲気を損ねていない事に驚いた。2016/04/18
りー
12
山本淳子さんの『枕草子のたくらみ』では“こんな人を同僚に働きたい”と思ったのですが、田辺さんの書く彼女は、なんというか、愛すべき人でした。上巻の「私は生きることが好きだ」というモノローグの通り、定子を魂の底から愛し抜き、男君たちと恋をして、ケラケラ明るい笑顔で「楽しかった」と去って行ったに違いない。一人目の夫=橘則光、二人目の夫=藤原棟世、男友達=経房、斉信、行成・・・それぞれに男性として個性的で素敵。彼らの魅力を引き出した大人の女性としての豊かさ。女としての魅力も強く感じた田辺さんの清少納言でした。2019/02/07