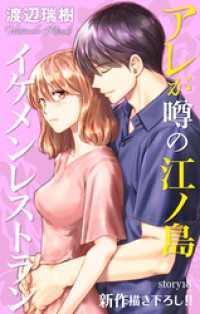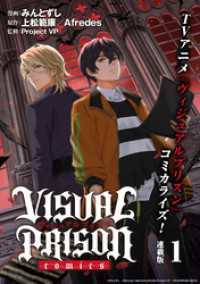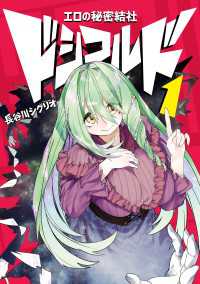内容説明
ドイツ製の液冷式エンジンを搭載、日本機離れした流麗な容姿からファンも多い「飛燕」。設計者、軍航空関係者らへの膨大な取材を敢行。開発の始まりから、日本初空襲のB‐25を試験飛行の折に追撃したエピソード、ニューギニア戦線での苦闘、本土上空でのB‐29への体当たり、そして五式戦への交代と、その激動の全軌跡を活写する力作。
目次
1 液冷戦闘機のあゆみ
2 “混血児”キ六一誕生
3 苦闘、ニューギニア戦線
4 決戦場フィリピンへ
5 本土上空の奮戦
6 遅すぎた五式戦の開花
著者等紹介
渡辺洋二[ワタナベヨウジ]
昭和25(1950)年、名古屋市生まれ。立教大学文学部卒業後、航空雑誌の編集者を経て、現在航空史の研究・調査をライフ・ワークとしている。現在までに取材した旧軍関係者は1000人を超え、その取材力、執筆内容の正確さには定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スー
18
三式戦飛燕はスマートな機体、日本機トップクラスの頑丈な翼でスピード制限がなく優秀な機体なのに日本の工業技術が低い為にエンジンの不調に泣いた悲劇の戦闘機。苦戦する海軍の手助けするためにニューギニア方面に進出するが、エンジン不調で稼働率が低く機体とパイロットを失っていく。B-29による空襲が激化すると今度は体当たり機となってしまう。上昇力とスピード不足解消を目指しエンジンの強化を計画するが、これまた不調に泣き、エンジンを空冷式に換装するや性能が向上し五式戦となるが、戦局は覆せず遅れた名機となる。2018/03/25
roatsu
11
本棚奥より。文庫化当時に読んだもの。日本陸軍の異色の戦闘機の生涯を追った決定版といえる記録。どの作品でもだが存命の元将兵をはじめ当事者達から得難い証言を引き出し、残された資料を分析する著者の努力は大変なもの。戦前日本の技術力では手に余るエンジンを採用したことが本機の苦闘の始まりだったがそうしたボタンの掛け違えはなぜ起こるのか、現代日本でも同じ問題は繰り返されていないかと考えさせられる戦記です。2015/04/03
roatsu
8
製造工場があった各務原市の民家などでプロペラスピナー等の部品が発見されたそう。実物の一部が発見されるとやはり遠くなった歴史が近づくように思う。まだ忘れられたまま日の目を見ることを待つ戦争遺構は多いのだろう。おそらくⅠ型用と思われるが、施された川崎緑という当時の独特な塗装を見てみたい。2015/08/08
零水亭
7
全く本の内容と関係なく恐縮ですが、2010年頃、東京の調布市にいた頃、この本を読んでいたら、陸軍の飛行第244戦隊で事務仕事をしていたというご婦人に話しかけられたことがありました。当時、雑誌SAPIOに板垣政雄軍曹(B29に体当たりして生還)のインタビュー記事が載っていたので、コピーしてお渡しました。
印度 洋一郎
5
日本軍の航空部隊に関しては、他の追随を許さない著者の作だけに内容たっぷり。日本軍には馴染みの薄い液冷エンジンを搭載した悲劇の戦闘機の誕生から終焉までを、関係者への丹念な取材で克明に記述。開発当初から問題山積ながらも実用化にこぎつけ、実戦配備されてからもエンジンを当時の日本人は扱いかねて故障が続出しながらも、南方でフィリピンで日本本土で苦闘が続く。前線のパイロットや整備員達の奮闘努力は涙ぐましいものがあったが、それが成果には繋がらなかった。それだけに、無理に無理を重ねざるを得なかった、当時の日本が哀しい2013/09/18