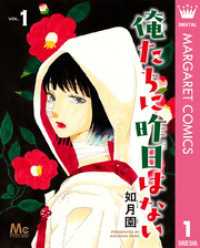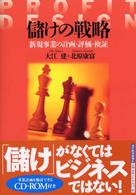内容説明
惑星“百合洋”が謎の消失を遂げてから1年、近傍の惑星“シジック”のイコノグラファー、クドウ円は、百合洋の言語体系に秘められた“見えない図形”の解明を依頼される。だがそれは、世界認識を介した恐るべき災厄の先触れにすぎなかった…異星社会を舞台に“かたち”と“ちから”の相克を描いた表題作、双子の天才ピアニストをめぐる生と死の二重奏の物語「デュオ」ほか、初期中篇の完全改稿版全4篇を収めた傑作集。
著者等紹介
飛浩隆[トビヒロタカ]
1960年島根県生まれ。島根大学卒。大学在学中に執筆した「ポリフォニック・イリュージョン」で第1回三省堂SFストーリーコンテストに入選、SFマガジン1983年9月号発表の「異本:猿の手」で本格デビューを果たす。以後、「象られた力」ほか、斬新なアイデアと端正な筆致による中短篇を同誌に発表するが、1992年の「デュオ」を最後に沈黙。そして2002年、10年ぶりの著作にして初の長篇『グラン・ヴァカンス 廃園の天使1』(ハヤカワSFシリーズJコレクション)を上梓、「ベストSF2002」国内篇第2位を獲得、第24回日本SF大賞の候補となった
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





乱読太郎の積んでる本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nico🐬波待ち中
77
地元出身という縁のある飛さんのSF物の短編4作品。普段SF物は読まないけれど、比較的読みやすい物語だったように思う。特に『デュオ』はSFというよりミステリー要素の強い短編でラストまで気が抜けない。ラストの文章がゾクゾクして余韻が残る。『夜と泥の』のしんと静まり返った真っ暗な沼の世界観も、何とも言えない余韻が漂って印象に残った。『呪界のほとり』のエメラルド色の竜ファフナーが可愛くて好き。すぐにドジって凹んで拗ねるファフナー。是非ペットとして飼いたい。2017/07/27
藤月はな(灯れ松明の火)
77
今まで読んできた日本SFのキャラクターで魅せるが故にどこかしらふわっとした感覚とは異なり、この作品集はグニャグニャとしたグロテスクでありながら硬質で美しいという矛盾を成功させている。この描写手法は皆川博子作品に似ているようにも感じます。表題作の官能を誘発させ得る物質としての「形」の規則めいた混沌、「デュオ」の常にありながらも絶対的に孤独で自由な死の匂い、「夜と泥の」の世界を再構築するために必要な「形」の再編集という、表裏一体描写は吐き気がするほど、惹かれる引力を持つ。2014/11/01
naoっぴ
75
あーびっくり。アイディアの宝庫のような中篇集だった。馴染みのないイメージに遭遇し、見たことのない質感に触れ、思いもよらない題材や考察に驚きながら未知の領域へと足を踏み入れていくよう。なんだかよくわからないけど、読むうちにこういうことかなと理解する。そうなると、いや待てもう一度始めから読まないとだめだ、と思う。難解だけど読み込まずにはいられない魅力がある。表題作では視覚言語という奇抜なアイデアにもびっくりしたけど、ラストの種明かしにも驚いた。いや、やっぱりもう一度読まなくちゃ(笑)2019/02/17
ホークス
73
著者の「廃園の天使」シリーズは、見棄てられた電脳世界の驚異と退廃が、美しく残酷に描かれていた。本書は初期の中短篇集で、これまた感覚的な冒険と言える傑作。「デュオ」の息詰まる様な意識世界の探究。「夜と泥の」は異界の不吉な手触りが原始的な恐怖を呼ぶ。中でも表題作は、イメージの洪水が感覚を激しく揺さぶる。図形が力を生む未知の世界を実感できてくるのが不思議だ。著者の「人間は世界を五感でしか感じとれない」という諦念が、世界に確固たるリアリティを与えている。ロジカルでエロティックという矛盾した魅力がある。2018/10/29
ざるこ
60
実は1度読んですぐ再読しました。少々難解な部分もあったのと、それ以上にもっと理解したいと思ったから。そしたら静寂はより静かに、崩壊は鮮明でド派手に…あっという間に世界に引きずり込まれます。特に表題作は読み直してみるとキーワードとなる文章や言葉があり、それに気付くと世界がもっと身近でリアルになる。内容は違うけど映画「インセプション」で観た空間が反転してるようなイメージ。シジックの街が折り畳まれていく…。緊張して読んだのか読後は脱力します。とにかくもう圧巻の1冊。SF好きな方にぜひぜひオススメしたい作品です。2018/11/19