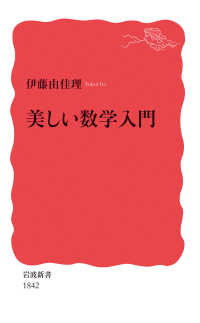内容説明
東南アジアの田んぼで、アフリカのブッシュで、岐阜の森で、世界中の人たちが、顔をほころばせて昆虫を味わっている。虫を採り、食すことで、生命と環境に五感で触れているのだ。バッタを狙い、カメムシを買い求め、ヘボを愛する中で、カラハリ砂漠の子どもは狩猟民として生きていく術を学び、ラオスの人は都市化で消えゆく「野生」を取り戻す。つまり昆虫食とは、自然と対話して恵みを得る智恵なのだ。日本中、世界中の昆虫食を追って旅してきた著者が描く、昆虫と人間が相互に深く交わる、豊かで美味しい営みの姿。
目次
序章 虫と営みを重ねて
第1章 営みが虫をはぐくむ―虫とともに生きる人々
第2章 大地という食卓―地球のグルメ、イモムシ
第3章 野生を取り込む智恵―カメムシの「臭さ」を生かす
第4章 虫に恋して―スズメバチのロマン
第5章 虫に向かって開く―昆虫食的認識へ
著者等紹介
野中健一[ノナカケンイチ]
1964年愛知県生まれ。名古屋大学大学院文学研究科史学地理学専攻中退。博士(理学)。立教大学文学部教授。専攻は地理学、生態人類学、民族生物学。昆虫食を取り上げて世界各地を訪ね、人々の自然資源の利用・環境認識・空間行動から「身近な自然と人間との関わり」を探る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sibasiba
15
昆虫は正直嫌いで食文化の本を読むのを趣味にしていたが、昆虫食関連は今まで避けていたが遂に挑戦。芋虫やイナゴなんかは知ってたけどカメムシ食べれるんだ。都市化で手軽に食べられる「野生」として昆虫食の需要が高まる傾向が意外だった。肉の2倍とか6倍でも売れてるとは。確かに日本でもやたらと天然物を持て囃す風潮があるし、もしかして日本でもブームが来るなんてこともありうるのか。2014/08/16
未来来
5
著者が出会った国内外の昆虫食について、採集、調理、背景等様々な点について述べられています。体験から書かれている為、内容が具体的で旅行記のようでしたが、単に世界各地の昆虫食を紹介するだけではなく何故食べるのかを考察したり、食べる対象や調理が異なる点を比較したりしつつ、異文化や環境との関わり方として纏めてあります。イナゴの佃煮が好きな身としては、とても興味をそそられました。また、日本での昆虫食がそうであるように、値の張る御馳走として他の国でも食べられているというのに驚くと同時に納得しました。《公立図書館》2009/12/24
dongame6
4
著者のフィールドワークによって得られた観点から昆虫食を「食糧」というより「食文化」として捕らえようとした本。肉や魚を得られぬ代用タンパク質と一般に考えられがちな昆虫食について新しい見識をもたらしてくれる一冊だと思う。東南アジアでの様々な昆虫食、市場で取引される食材としての虫、アフリカで売買されるイモムシの干物など、代用食品ではなく豊かさとして見た昆虫食については特に面白かった。また、日本での過去、現在の昆虫食についても触れられており、蜂の子「ヘボ」を巡る人達の物語は一読の価値があると思う。2013/05/29
takao
3
ふむ2022/08/30
田蛙澄
3
イナゴくらいなら食べたことはあるが、蜂の子やカメムシ、蛾の幼虫、セミ、バッタなどを廻って岐阜や沖縄、ベトナム、ラオス、南アフリカでの昆虫食とそれに関わる人々の暮らし、環境や生態の見方を描写し、単に話や頭のレベルでない実体験としての異文化理解の重要性を語るところが素晴らしかった。カメムシはパクチーのような臭いだと聞くが、熱湯をかけながら臭い物質を出させる南アフリカのやり方とむしろ臭いを生かすベトナムの食べ方の対比など、同じ昆虫食でも文化によって調理法や食べ方が多様なのが面白い。昆虫を食べたくなる一冊だった。2017/02/19