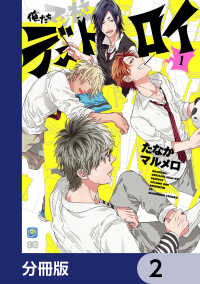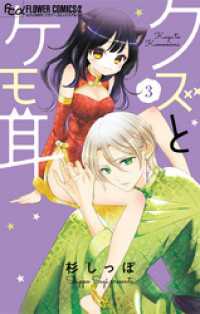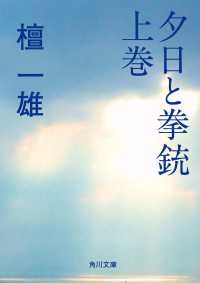出版社内容情報
「してヤラれた」と思った「雪国」の冒頭。生きている文章書き手、志賀直哉。さりげない文体の名人、井伏鱒二。繰り返し読んで飽きない「陰翳礼讃」――。最後の文士とよばれた著者が、多種多様なスタイルの名文を小説家ならではの視点で読み解き、すぐれた文章とはどんなものかを綴る。読書案内にして名文鑑賞の書。〈解説〉蜂飼耳
目次より(一部抜粋)
自然のエロス――川端康成『雪国』
生き物の死――志賀直哉「城の崎にて」
感覚とモンタージュ――横光利一『上海』
光と影――谷崎潤一郎『陰翳礼讃』
ある死生観――尾崎一雄「虫のいろいろ」
詩美的感覚――梶井基次郎「檸檬」
性の描写――山本周五郎『青べか物語』
抑制と恥じらい――伊藤整『若い詩人の肖像』
ユーモアとペーソス――井伏鱒二「山椒魚」
典型的自画像――太宰治『人間失格』
切腹の描写――三島由紀夫「憂国」
戦場の死と生――大岡昇平『俘虜記』
絶体絶命の時――吉田満『戦艦大和の最期』
女であること――林芙美子「晩菊」
砲丸を投げる――小林秀雄「オリムピア」
夢を描く――内田百閒『冥途』
老年のエロス――結城信一「空の細道」
女人礼讃――室生犀星「えもいわれざる人」
着物を描く――芝木好子「京の小袖」
新しい血――三浦哲郎『初夜』
一語の重さ――佐多稲子『夏の栞』
戦場を見る――開高健『輝ける闇』
沈黙と虚無――佐藤春夫「『風流』論」
リング上の闘い――沢木耕太郎『ドランカー〈酔いどれ〉』
吉行淳之介『女のかたち』抄
死への鎮魂――吉村昭『星への旅』
厄介な生き物――阿部昭『言葉ありき』
生命の復活――北條民雄『いのちの初夜』
古都の異人――島村利正『奈良登大路町』
老いの果て――耕治人『天井から降る哀しい音』
完結した人生――司馬遼太郎『歴史と小説』
美しいものとは――岡部伊都子「青磁」
海景の中の人生――水上勉「寺泊」
権威を笑う――井上ひさし「パロディ志願」
物狂おしさの果て――瀬戸内晴美『放浪について』
土への夢――深沢七郎「生態を変える記」
ある狂熱者――棟方志功『板極道』
手でつかむ――柳宗悦「雑器の美」
芸術とは?――吉田秀和「ヨーロッパの夏、日本の夏」
エロスの詩――野
【目次】
内容説明
「してヤラれた」と思った『雪国』の冒頭。生きている文章の書き手、志賀直哉。さりげない文体の名人、井伏鱒二。繰り返し読んで飽きない『陰翳礼讃』―。最後の文士とよばれた芥川賞作家が、多種多様なスタイルの名文を小説家ならではの視点で読み解き、すぐれた文章とはいかなるものかを綴る。読書案内にして名文鑑賞の書。
目次
自然のエロス―川端康成『雪国』
生き物の死―志賀直哉「城の崎にて」
感覚とモンタージュ―横光利一『上海』
思想と感情―夏目漱石『草枕』
光と影―谷崎潤一郎『陰翳礼讃』
ある死生観―尾崎一雄「虫のいろいろ」
死の凝視―芥川龍之介『或阿呆の一生』
詩美的感覚―梶井基次郎「檸檬」
性の描写―山本周五郎『青べか物語』
油絵的文体―有島武郎「生れ出づる悩み」
水彩画的文体―永井龍男「粗朶の海」
非情の眼―丹羽文雄『鮎』
抑制と恥じらい―伊藤整『若い詩人の肖像』
ユーモアとペーソス―井伏鱒二「山椒魚」
典型的自画像―太宰治『人間失格』
切腹の描写―三島由紀夫「憂国」
広島・原爆の日―原民喜『夏の花』
戦場の死と生―大岡昇平『俘虜記』
死に至る挑戦―島木健作「赤蛙」
庭を見る―井上靖「日本の美と心」〔ほか〕
著者等紹介
八木義〓[ヤギヨシノリ]
1911(明治44)年、北海道室蘭市生まれ。小説家。38年、早稲田大学文学部仏文科卒業。横光利一に師事。満州理化学工業に入社し大陸に渡る。44年に『劉廣福』を発表、その芥川賞受賞を出征中の中国湖南省で知る。復員後、空襲で焼死した妻子を偲ぶ『母子鎮魂』、自伝的作品『私のソーニャ』などを発表。77年『風祭』で読売文学賞、88年日本芸術院恩賜賞、90年菊池寛賞を受賞。1999(平成11)年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。