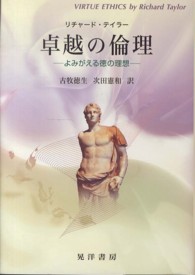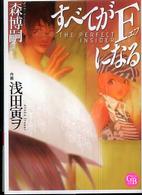内容説明
同じ洋服を着ているのに、日本人と西洋人の歩き方が違うのはなぜか―。立ち方、坐り方、服の着方、履き物の履き方など、なにげない日常の動作から浮かび上がってくる、現代日本人の身体にしみこんだ武道、茶道、能薬、禅など伝統文化の深層。「身体」を通した画期的な日本人論。
目次
第1章 立居振舞いの論理
第2章 履物と歩行様式
第3章 和装の身体技法
第4章 日本人の坐り方
第5章 身体の自然性
終章 方法論
著者等紹介
矢田部英正[ヤタベヒデマサ]
1967年東京生まれ。筑波大学大学院修了(体育学修士)。学生時代は体操競技を専門とし全日本選手権等に出場。国際日本文化研究センター研究員を経て、文化女子大学大学院にて和装と身体のかかわりを研究し博士号取得(被服環境学)。姿勢研究の一環として99年より椅子の開発に着手、デザインレーベル「コルプス」を発足。現在、お茶の水女子大学および武蔵大学非常勤講師。武蔵野身体研究所主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネムル
8
日本人のたたずまいが漠然とした精神論や象徴論に流れず、西洋人との所作(歩く、坐る、着こなす)の差異を農耕/狩猟文化の背景や帯/コルセットといった服飾の点から明快に語っている。一番興味深く驚いたのが、花魁とポックリから日本女性の歩行の媚態を「「覆い隠すこと」と「見せること」の均衡のずれ、技法的な意味では「整える」ことと「崩す」ことの均衡のずれを生じさせる」ことというところ。これが後に古代ギリシアと日本のたたずまいの違いにつながっていく。2013/06/26
Rami
3
人の身体や道具のあり方には、理由や歴史がある。終章の「方法論」がとてもよかった。自分で自分の研究を解説するって、自信と勇気がないとできないと思う。2021/10/14
さちめりー
2
今年度 著者の担当する #放送大学 #面接授業 でこの著書が教科書となっていて予習が必要なため目を通したが想像以上におもしろかった。教養深く考察されていて私の好きな東西文化比較も盛り沢山だ。運慶の大日如来坐像の姿勢の解説まできける。この著書本人の授業が受けられるなんてワクワクする。2023/09/28
yuka
2
日本人と、(乱暴な言い方をすると)、それ以外の人と、なぜあんなにも歩き方や動き方が違うのかとずっと思っていたことがようやく分かった。重心の位置や履物・着物との兼ね合いで、あれがベストなのだ。 ヨーロッパのダンスをしている私は、日本人として克服しなければいけないことがたくさんあったが、なぜそんなにもたくさんの事を克服しなければならなかったのかも、ようやく理解した。 また、日本人ダンサーの考え方の癖についても、すごく理解が進んだ。 良い本だ! 再読必至!2023/01/15
hizumi
2
普段着慣れない現代人がいわゆる必要に応じて着る時の着物ってバキバキに直線的で糊のきいたシーツみたいに固そう。夢二の絵に出てくる女の人の着物はたおやかで身体の形によく馴染んでいるというか、だいぶ使い込んでくたっとした布団着ているみたいで、そういう画風なのかと思っていたけど、「くびれ」か、なるほど。。2022/10/12