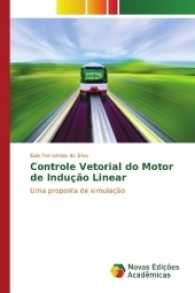出版社内容情報
謎にみちた日本民族の生成を神話学・歴史学・考古学の最新の成果によって解明、神話の中の真実を探り、女王卑弥呼を語り、日本の歴史の夜明けを描く。
内容説明
第二次大戦後、画期的な進歩を示した歴史学と発掘成果いちじるしい考古学とは、古事記・日本書紀の世界に、まったく新しい光を投げかけた。これら諸学を総合的に協力させることにより、従来の歴史書には見られない鮮明さで、古代日本はその姿を現すこととなった。巻末に森浩一「四十年のちのあとがき」を付す。
目次
日本の神話
石器時代の日本
歴史のはじまり
謎の世紀
最初の統一王朝
古代国家への歩み
著者等紹介
井上光貞[イノウエミツサダ]
1917年(大正6)、東京に生まれる。明治の元勲井上馨の曾孫。桂太郎の外孫にあたる。42年(昭和17)、東京帝国大学文学部国史学科卒業後、『帝室制度史』の編纂に従事。50年、東京大学教養学部助教授、61年、文学部助教授、67年に教授となり、78年に退官。東京大学名誉教授。81年、国立歴史民俗博物館初代館長に就任。専攻は日本古代社会思想史。1983年(昭和58)2月、逝去
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Vakira
51
日本の歴史の黎明期。旧石器時代、縄文時代、弥生時代、飛鳥時代まで。最初は古事記、日本書紀の内容が基本なので読んだ事はありませんが知ってる神話の数々。天照大御神、須佐之男命、大国主命・・・etc。手塚治虫の火の鳥の「黎明編」「ヤマト編」が蘇る。卑弥呼が魏志倭人伝に登場するまでは日本の記録は無し。邪馬台国は何処だったか?なんて未だに判らずロマンがある。ロマンと言えば理系の僕が思うに鉄の活用だ。青銅から鉄へ。鉄の活用が歴史を大きく変えたと思う。鉄使師とか炎使師とか。磁石を持っていれば砂鉄を探せる。 2020/05/22
kenitirokikuti
11
(先)古代史が教科書などでどのように記述されてきたか、その移り変わりを確かめている。本書の刊行は1965年、かつて歴史として語られた記紀万葉の神話や伝説を多方面から照らすことに頁が費やされていることに特徴がある。明治時代に大森貝塚が発見され、古代の土器が西洋の考古学と接続したが、それでも関東ローム層の下から石器が出土すると認められたのは戦後のことであった。現在では、列島での土器の使用については世界でも最古に相当すると見られている(ヤマトより古く、関連も乏しそう)▲平成には三内丸山遺跡への言及が必要になる2023/11/02
訪問者
6
『古事記』、『日本書紀』のテキスト分析から始めているのは極めてユニーク。また1964年の著作であり、それまで5〜6千年前と考えられていた縄文時代が、数年前の放射性炭素年代測定により1万年と2千年前から縄文時代とされたことが驚きを持って書かれている。2024/01/09
takeshi3017
6
中央公論の歴史本第1巻。古事記などの日本神話から日本の歴史の夜明けを描く。日本の神話、石器時代の日本、歴史の始まり、謎の世紀、最初の統一王朝、古代国家への歩みなど。特に日本神話は知らない話が多かったので参考になった。詳細→ http://takeshi3017.chu.jp/file9/naiyou31001.html2022/01/13
あしお
6
学生時代に読んだ本の再読。日本の通史を読みたいと何冊か読んだけど、最近の歴史の本は「科学的」過ぎて味も素気もない感じでつまらないのが多いですね。むしろ昭和40年代のこの本が「古代史へのロマン」を掻き立てられて楽しいです。歴史観というのはイデオロギーと結びつきやすいから中立を保とうとすれば無味乾燥なものになるんでしょうね。でもこの本は中立的でありながら、戦後の学問の自由が認められた時代の闊達な雰囲気に満ちています。現代の考古学の成果から見れば、古い説も多いのだろうけど。それでも、十分楽しめます2017/12/27
-
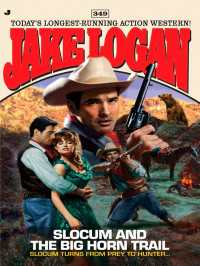
- 洋書電子書籍
- Slocum 349 : Slocum…
-
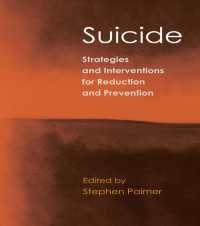
- 洋書電子書籍
-
自殺:介入と予防の戦略
Suic…