内容説明
1879(明治12)年、お茶屋「大友」に生を受けた多佳は21歳で落籍されるも、2年後、相手に先立たれ、再び芸妓に。和歌や絵を嗜む“文芸芸妓”として名を馳せた多佳は多くの文人・画家たちと交流、祇園を文化サロンにまで高める。華やかな祇園を舞台に愛と孤独に揺れた生粋京女の一生を、雅豊かに映し出す。
目次
雨の追善会
黒い眼
舞と音曲
歌才の芽生え
芸妓多佳
中村楼の出会い
「九雲堂」の女主人
風流ぬす人
文人たちと多佳
伽羅の香り
雪の京都
鴨川を隔てて
祇園の誇り
漂白の日々
滅びの支度
あぢさいの花
著者等紹介
杉田博明[スギタヒロアキ]
1936(昭和11)年、京都府生まれ。同志社大学卒。1960(昭和35)年、京都新聞社入社。文化部、美術部、社会部を経て、編集局編集委員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaoru
6
谷崎や漱石など文豪と交流のあった「文藝芸妓」磯田多佳の生涯を描いた本。祇園の芸妓から陶器店「九雲堂」の経営者、お茶屋「大友」の女将として生き、俳句や書画を嗜むなど風雅に生きた多佳女。画家の浅井忠や岡本橘仙などとの関わりも語られる。漱石との交流にも多くのページが割かれる。「梅見事件」のすれ違いのあと、漱石が彼女に宛てた手紙は冷静な彼に似合わず激烈だ。漱石の心を乱す何かが多佳にあったのだろうが、両者の埋めがたい齟齬も感じる。「京都でしか生きられない女」だった多佳を古き良き日本への哀惜とともに綴った優れた著書。2018/06/19


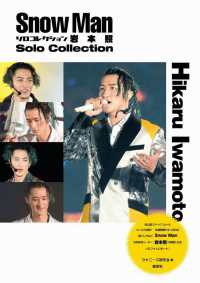

![空色のクリームソーダガラスペン茜空 [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48470/4847073304.jpg)




