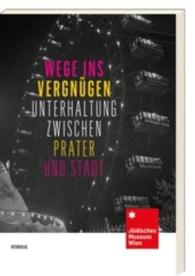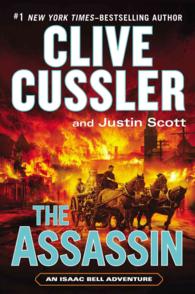内容説明
権力に抗し、教団を捨て、地獄の地平で痛憤の詩をうたい、盲目の森女との愛に惑溺してはばからなかった一休のその破戒無慙な生涯と禅境を追跡した谷崎賞受賞に輝く伝記文学の最高峰。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さっちも
14
晩年の道歌「色の世界に色なき人は 金木仏石ほとけ」人間の自然を否定して何処に人生があるのかという詩にドキリとさせられる。40以上離れた盲女を側におき、80過ぎてもその淫行の数々を詩に残した一休。目の前の世界の感触や実感をもっと大事に素直に生きるべきではないかと言ってる気がする。茶道の開祖村田珠光をはじめ、能、連歌、画家の数々が一休を慕い、大徳寺に集まってサロンと化したのは、既存の価値を逸脱し、生きる事の根源を直視した「くそまじめ」な禅の心境に惹かれたからではないか。思った通り一休は手に負えなかった。2017/10/20
オッキー
6
★★★★☆2024/12/20
アメヲトコ
5
風狂の僧、一休の人生を描いた長編評伝。考証が中心で引用がかなり多く、正直なところかなり読みづらいですが、著者自身の徒弟時代と重ね合わせた修業期の描写、晩年の愛人・森女の造型などはいかにも水上節という感じ。私自身は一休のある種のこれ見よがしな言動が気になってあまり思い入れができなかったのですが、対象に迫る著者の迫力ある筆致には感じるものがありました。2018/05/16
織沢
4
面倒くさい本だと思う。引用は多いし、引かれる文章も普段親しんでいる文章とは違っていて、いちいち詰る。しかし時折、無性に面白いと思わされる時もあった。私は半分ほど読んだ辺りで本書の読書会に参加し、以降を読むモチベーションを失ったので、読書を放棄してしまうことにした。同じ谷崎賞作だと瀬戸内寂聴の『花に問え』が僧侶の評伝ということで近しい印象を持つ。寂聴が対象を鷲掴んで、その心象を描こうとするのに対して、水上は霧の向こうの対象を様々な資料を頼りながら、もがきつつ迫る感じがした。2021/06/24
あきこ
3
一休と言えば「とんち」でしょ。大徳寺だね、くらいの知識で読んでみた。違う、私の思っていた一休はもっとのんきな一休だったが実際の生き方は壮絶である。仏教界の僧の堕落を嫌い、終生孤独ゆえの頑固さ、地に足を付けることの大切さを守りぬいたように思う。晩年の盲人森女との愛情は一休の生き様を凝縮しているかのように感じる。生きること、人として何が大事なのかということが二人の関係から伝わってくるように感じた。もう少し一休について知りたくなった。2020/05/14
-

- DVD
- 手錠のままの脱獄