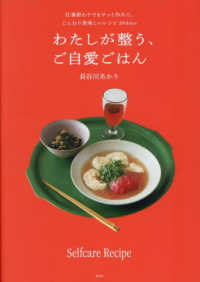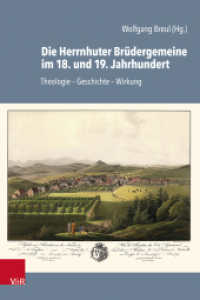内容説明
『全体主義の起原』『人間の条件』などで知られる政治哲学者ハンナ・アーレント(1906‐75)。未曽有の破局の世紀を生き抜いた彼女は、全体主義と対決し、「悪の陳腐さ」を問い、公共性を求めつづけた。ユダヤ人としての出自、ハイデガーとの出会いとヤスパースによる薫陶、ナチ台頭後の亡命生活、アイヒマン論争―。幾多のドラマに彩られた生涯と、強靱でラディカルな思考の軌跡を、繊細な筆致によって克明に描き出す。
目次
第1章 哲学と詩への目覚め―一九〇六‐三三年(子供時代;マールブルクとハイデルベルクでの学生生活 ほか)
第2章 亡命の時代―一九三三‐四一年(パリ;収容所体験とベンヤミンとの別れ)
第3章 ニューヨークのユダヤ人難民―一九四一‐五一年(難民として;人類にたいする犯罪 ほか)
第4章 一九五〇年代の日々(ヨーロッパ再訪;アメリカでの友人たち ほか)
第5章 世界への義務(アメリカ社会;レッシングをとおして ほか)
第6章 思考と政治(「論争」以後;暗い時代 ほか)
著者等紹介
矢野久美子[ヤノクミコ]
1964年、徳島県生まれ。2001年、東京外国語大学大学院博士後期課程修了。学術博士。現在、フェリス女学院大学国際交流学部教授。思想史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 6件/全6件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
- 評価
新聞書評(2013年3月~2014年12月)の本棚
- 評価
京都と医療と人権の本棚
- 評価
新聞書評(2015年)の本棚
- 評価
芸術系な人文・文学好き書店員F本の気になる新刊本棚
- 評価
「サイエンス周辺」 備える本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
296
新書大賞上位にくい込んでるからどんな本かと思い読んでみた。伝記だなと思った。あとナチズムの影響は当時の思想にも影響あったのだなと感じた。2015/02/28
遥かなる想い
221
2015年新書大賞第3位。 20世紀を生きた政治哲学者ハンナ・アーレント の人生を描く。 1906年にドイツでユダヤ系の親の元で生まれた アーレントはある意味 20世紀のドイツの歴史を 体現した人物であり、その人生は興味深い。 ナチ台頭のドイツで人々は何を考え、 生き抜いたのか..馴染みのない哲学の世界.. だが知識人の大移動という視点は新鮮。 20世紀がアメリカの時代となる背景が アーレントの人生からも見え隠れする。 2016/02/07
はっせー
130
ハンナ・アーレントさんの著書を読むためにこの本を読み直した。新しい発見が多くあった!ハンナ・アーレントさんの人生がまとめられている。それだけではなく、著書の解説も書いてあるため勉強になった。ハンナ・アーレントさんの思考で面白いものがあった。それは自己嫌悪になってしまった人間は、何かの忠実な者になりたくなる。そうなってしまうと自分より集団が優先したり、他者の決定に無造作に従いたくなる。その言葉はナチス・ドイツになる過程を研究したときの思考である。いまの世の中にも充分刺さる言葉ではないかと思った!2021/12/11
(haro-n)
119
アーレントの生涯を、彼女の家族や友人、恩師らとの交流や彼女の著書の紹介を通して、彼女が何に直面し、何を考え、何を理解しようとしたのかを中心に説明する。著者の熱意も伝わってくる良書。アーレントは全体主義の危機をもたらす「思考欠如」に陥らないために、自分との対話と世界と関わるための公的な行為を重視する。しかし、その時の公的なものや世界とは中心化されたものではなく、人々が集まり、自由に言葉を交わし、判断を行使する公共の空間の中で生じる下からの(権)力のことである。彼女の人生と人間に対する誠実な眼差しを感じた。2018/03/04
skunk_c
85
良書。若い頃書店で『全体主義の起源』を見かけながら、手を伸ばさなかった自分を(今古書で高いのよね)悔やむ(笑)。若い頃の過酷な暮らし(ドイツのユダヤ人でナチス成立頃にちょうど青年、そして苦労してアメリカへ)という自己の立ち位置から、生きて考え、動く自分を徹底して見つめる彼女の姿をコンパクトに叙述する。アーレントの姿勢は「思考停止」に陥りやすい組織の中の個人という問題にも通じるし、その一貫性には驚愕すら覚える。彼女が今のイスラエルを見たとしたら何と言っただろうか。ポピュリズムを論じる際の本質があると思う。2023/04/27
-
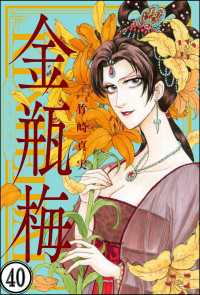
- 電子書籍
- まんがグリム童話 金瓶梅(分冊版) 【…