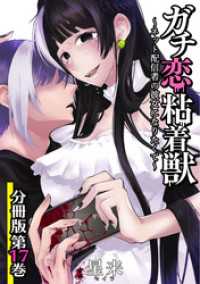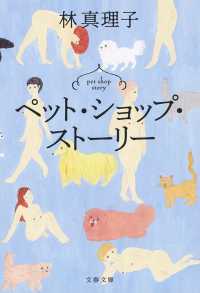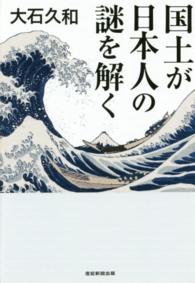内容説明
アメリカ型の経済学教育の導入により、経済学の一元化が進み、自由な思考にとって最も貴重な多様性が失われている。本書は、主流派が真剣に読まなくなった、マーシャル、ケインズ、サムエルソン、ガルブレイスらの経済学を再検討し、今日的視点から彼らの問題意識や問いかけのもつ意味を考察するものである。異端派を排除してきた「ノーベル経済学賞」の問題点をも指摘しつつ、相対化を忘却した現代の経済学に警鐘を鳴らす。
目次
第1章 現代経済学の黎明
第2章 マーシャル経済学の魅力と限界
第3章 ケインズ革命
第4章 サムエルソンの時代
第5章 異端派ガルブレイスの挑戦
第6章 リベラリズムの後退
第7章 ノーベル経済学賞の憂鬱
著者等紹介
根井雅弘[ネイマサヒロ]
1962年(昭和37年)、宮崎に生まれる。1985年、早稲田大学政治経済学部卒業。京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。京都大学経済学博士。京都大学大学院経済学研究科教授。専攻、現代経済思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
37
金融の世界には、ガルブレイスによれば、「新しい」商品が発明されるたびに、それを歓迎する奇妙な雰囲気がある。しかし、「新しい」とされたものも、実は、昔からある「てこ」(例えば、チューリップ狂のときには、小さな球根が巨額の貸付の「てこ」となった)の再発見にすぎない場合が多い。/2006年初版の本。リーマンショック後であれば、著者もっと書き加えただろうなあと思いました。2020/09/29
masawo
7
マーシャル以降の主要人物を紹介しつつ、著者の魂が最も込められているのはノーベル経済学賞と経済学の多様性について述べられている第七章。政治情勢に左右されやすい経済学という学問の行く末について熱く警鐘を鳴らしている。学問の面白さがギュッと詰まっており、模範的な新書だと思う。2021/06/20
ヤギ郎
7
現代経済学の本。門外漢なので,本書の良し悪しを評価できないが,名前を見聞きした学者さんが学問界にどのような影響を与えてきたを知ることができた。ノーベル経済学賞について記されていて,興味深い考察を得た。2018/07/02
Saiid al-Halawi
4
現代経済学史の歴史的な豊かさにも関わらず、今の経済学のトレンドには公正さと政治的なバランス、そして何よりもダイバーシティが足りない、というのが本書のテーマ。ガルブレイスとかヴェブレンとか、好きな人らにスポットが当たってて楽しく読んだ。2013/10/10
Nさん
3
米国経済学会の誕生から現代に至るまでの経済学(会)のトピックを紹介する一冊。本書の主題は「経済学の多様性」の大切さを解くことだ。主流派経済学の他を認めない態度は、経済学徒の私も感じる所がある。テクニカルな理論に基づいた演習・数値計算だけを積めば良し!マルクス?ヴェブレン?シュンペーター?を学ぶ必要ある?みたいな大学院の先輩を多数見てきた。複雑な現実と向き合うヒントこそ、主流派以外にあるのではないだろうか。「新古典派総合」の瓦解、異端派ガルブレイスの挑戦、リベラリズムの後退など、物語としても読ませてくれる。2020/01/23