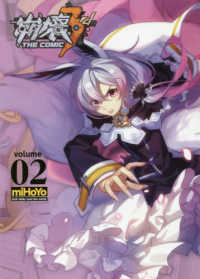内容説明
本書は、豊富な実例を引用しながら、日本人の思考様式と日本語の姿や表現との関わりを探る試みである。
目次
1 発話の場面、発せられる表現―なぜ客観的叙述が取りにくいのか
2 「私」中心の視点―日本語的な内と外とは何か
3 対人意識に基づく表現―人間関係がどう言葉に現れるか
4 日本語の情意性と文学―対象把握に現れる表現者の心
5 受身的発想に基づく言葉―受身で客観性をどう示すか
6 「成り行き」の論理―他力的発想と近視眼的思考
7 会話の論理と表現の論理―場面即応型言語の立脚点
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びす男
53
言葉は人の思考を形づくる。日本人なら、黙っていても「何をしよう」「どうしよう」と日本語で考えているだろう■もし言語に限界や特徴があれば、それは言語圏が抱える文化のありようにも影響するのではないか……。興味深いテーマだ。虹について、「3色」という文化圏と「7色」という文化圏があると聞く。語彙がなければ認識も難しい。思考するのはもっと難しい■日本語は主観的表現が好んで使われ、客観視が苦手らしい。慣用句に潜む視覚や触覚、受け身の多用という例に、つい膝を打つ。普段使っている言葉を仔細にあらためる感覚が新鮮だった。2019/11/18
サアベドラ
14
日本語の表現形式から日本人特有の考え方、思考の癖を探るエッセイ。著者は早大名誉教授で、『日本語をみがく小辞典』(講談社現代新書)を書いた人らしい。日本語では受け身表現が多いから云々、手に関することわざや慣用句が多いから云々、といった具合に話が日本語のなかに限定されていて他言語との比較がほとんどなく、そもそもそれって単なる著者の印象じゃないのと思えるような箇所もけっこう多い(特に第6章)。日本語に興味のある人の暇つぶしにはいいかもしれないけれども。2014/05/05
愛奈 穂佳(あいだ ほのか)
6
【ココロの琴線に触れたコトバ】ともかく他人や社会と接する貴重な場面や状況では、全体像の基本を押さえておくことが日本では特に大切で、その場での自由な発想が受け入れにくい傾向にある。結婚式の仲人の式の進め方やスピーチしかり。その他各種の式次第。それらが伝統的な形式に縛られているため、厳粛ではあるが、「真面目すぎて面白くない」という批評が外国人の口から漏れる。2016/01/07
juunty
2
英語を日本語に翻訳していると「(あなたの)本を、(私に)貸してください。」という形で「あなた」「私」を独立して翻訳することに違和感がある。これは文法的な翻訳として正しいが、日本語は無意識の言葉遣いのなかに「予め自分の領域と他人の領域を設定する」価値観をもっている。そのため言葉の中に「あなた」「私」を明確にする必要性が低い。一方英語などの他言語は言葉の中に多くの機能を含めず、文章の中において「あなた」「私」などの領域を明確にする言葉を設置していく。これは言語の優劣ではなく、特徴である。2020/06/18
Takashi Inoue
2
日本語の視点が全体から個に向かい、英語の視点が個から全体に向かう傾向があるということについて、納得はいくものの、批判めいた書き方が多く、読んでいてだんだんと気が滅入る。筆者自身、「日本語が豊かな言語」というように、その豊かさについて言及し、自国語やその視点に誇りを持たせてくれる内容であってほしかった。2016/08/23
-

- 和書
- 秘書概説