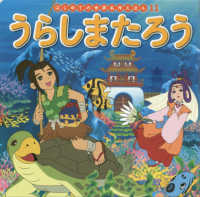出版社内容情報
明治十七年秋、明治国家がまさに確立せんとする時期、秩父盆地を中心舞台に武装蜂起し、一時・無政の郷・を現出した農民たちのエネルギーは、どのようにして生まれたのか。事件の策源地に生まれ育ち、この事件を歴史家としての原点と考える著者は、困民党の反権力意識、行動形態、組織など、事件において農民たちの主体的基盤をなしたものを解明する。ここには、商品経済の波にのみこまれた農民の変革精神が生き生きと流れている。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
松本直哉
19
自由という言葉が作られて間もない明治17年という時代に、この概念を血肉化した人々がいたことに驚く。自由民権運動と関係を持ちながらも核になったのは貧窮に喘ぐ農民。明確な指揮系統と厳格な規律(掠奪や強姦をした者は斬など)のもとに、攻撃の目標を自分たちの貧困の元兇である高利貸に絞り、焼き討ちをかけ証文を焼く。炊出しをさせる民家への鄭重な態度も印象的。同時代のパリ・コミューンやアナキストの運動など、世界的に自由を求める機運が盛り上がったことも興味深い。自らも秩父出身の著者の共感に満ちた筆致。2017/07/07
takeapple
11
フランス革命の研究家で、秩父出身の井上先生の著書。初めての本格的秩父事件の概説書というべき古典的名著。思えば大学一年の時、憲法学の先生にこの本を読む自主ゼミに誘われたことがあったけれど、当時は考古学の勉強に忙しく参加しなかったのが悔やまれる。 ここにも、会津の先生と呼ばれた2人の男が出て来る。うち一人は生死不明のように読めるのだが。最新のものも読んでみたい。2017/02/24
ニコン
11
【図書館】2015/02/16
takao
3
☆絹と生糸が産業。明治は好不況の差が大きかった。不況時なので、税の負担が大きくなった。 高利貸の焼き討ち、打ち壊しが行われた。2017/03/13
ゆゆる
1
う2024/07/14
-

- 電子書籍
- 働くふたりのごほうび飯(1)