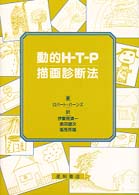出版社内容情報
「文明の生態史観」など独自の思想を展開してきた「知の探検家」梅棹忠夫。薫陶を受けた研究者たちが挑んだ、白熱の議論を再現。
内容説明
自分の足で歩き、自分の眼でみて、自分の頭で考える姿勢を貫く比較文明学者・梅棹忠夫は、「文明の生態史観」「情報産業論」「遊牧の起源」など独自の思想を展開し、現在も版を重ねるベストセラー『知的生産の技術』を著すなど、戦後の社会に大きな影響を与えてきた。梅棹の薫陶を受けた研究者たちが論戦を挑んだ、米寿記念シンポジウム「梅棹忠夫の世界」を再現。
目次
第1部 知の探検家・梅棹忠夫(モゴール族探検記;中洋の発見;文明の生態史観 ほか)
第2部 シンポジウム―梅棹忠夫の世界(よみがえったモンゴル研究―『狩猟と遊牧の世界』;「文明の生態史観」と今日の世界;「情報産業論」―世相と未来を見とおす導きの書 ほか)
第3部 時代の証言者 文明学(足で切り開いた世界史観;本と昆虫を愛した幼少期;山は「総合科学研究所」 ほか)
著者等紹介
石毛直道[イシゲナオミチ]
1937年生まれ。国立民族学博物館名誉教授。文化人類学、食事文化・比較文化。農学博士
小山修三[コヤマシュウゾウ]
1939年生まれ。吹田市立博物館館長・国立民族学博物館名誉教授。民族学(オーストラリア・アボリジニ)、考古学(縄文時代)。Ph.D.(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かりん
2
3:挑むというか梅棹万歳。遊牧、文明の生態史観、情報産業論を網羅。コミュニケーション論、情報論の違い。幼獣を人質。遊牧社会に内在する軍事性。(情報の取引は)でたらめをやろうとおもえば、どのようにでもでたらめなことになりうる。われわれの多くは、情報の効用が誰にとっても同じだと考え、他の買い手と同じ金額を支払えば妥当な取引になると思っているのではないか=貧しい選択。知的消費≠蓄積。人間の営みを「遊びと楽しみ」に変える(例:農業→園芸)。真善美悦論。心が耕されている中東。明るいペシミスト。2009/07/11
ノンミン
0
梅忠さんという巨匠を改めて、すごい、と感じる本でした。偉大な人は、様々な視点を持っていることがよくわかりました。2017/11/11
カネコ
0
◎2010/03/22