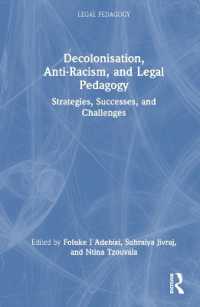出版社内容情報
小説は小説を書いている時間、読んでいる時間にしかない。---『小説の自由』『小説の誕生』につづく小説論完結篇。故小島信夫氏への追悼作品も付す。
内容説明
小説は、人を遠くまで連れてゆく。書き手の境地を読者のなかに再現する小説論。
目次
1 私たちの生を語る言語
2 緩さによる自我への距離
3 グリグリを売りに来た男の呪文
4 涙を流さなかった使徒の第一信
5 ここにある小説の希望
6 私は夢見られた
7 主体の軸となる現実は…
8 われわれは自分自身による以外には、世界への通路を持っていない
9 のしかかるような空を見る。すべては垂直に落ちて来る。
10 遠い地点からの
著者等紹介
保坂和志[ホサカカズシ]
1956年、山梨県生まれ。鎌倉で育つ。早稲田大学政経学部卒業。1990年『プレーンソング』でデビュー。93年『草の上の朝食』で野間文芸新人賞、95年『この人の閾(いき)』で芥川賞、97年『季節の記憶』で平林たい子文学賞、谷崎潤一郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
12
この本の中で保坂和志は何度も感動・感激していてそこが素晴らしい。ニーチェの「永劫回帰」と石で宮殿を作った郵便配達人シュヴァルの話がつながった後の結句が素晴らしい。小説家が小説を書く時の感覚を、呼び起こしながら小説を読むこと。果たしてそんなことができるのだろうか。そう考えさせてくれるのが素晴らしい。ところで、「素晴らしい」の語源は「すばる」、つまり「狭くなる」という意味の言葉らしいのだが、この本は思考が相当に狭い道を通って本質を掴まんとする体験を読者に与えてくれるところが素晴らしい。2017/07/11
ぽち
9
この本は2008年に刊行されたもので、購入したのは直ぐじゃなかったとは思うけどたぶん10何年かは積読していて、というかこの前の二冊『小説の自由』『小説の誕生』もだいぶ時間をかけて読んでいたので読み出すが遅くなった、でさらにゆっくり、場所によってはだいぶ苦戦しながら、この長い小説論を書籍化した三冊を、とうとう読み終わってしまった。小説論、というか連載時のタイトル『小説をめぐって』が本当にそのままで、小説を中心にして小説のことも世界のことも世界に浮かぶわたしのこととかもその他のこととかも、いろいろ考える、2023/06/12
勝浩1958
6
保坂氏の作品はとても難解で分からないことだらけなのですが、そのような中でもとても印象的なフレーズが宝石のように煌めいているので、私を惹きつけて止まないのです。この作品の感想は特にうまく述べることができませんので、フレーズの列挙を感想に替えます。「この連載を通じて「因果関係」という言葉を何十回書いたか見当がつかないけれど、一つか二つかせいぜい数個の入力に対して一つの結果が出てくるというふつうにイメージされる直線的な因果関係の思考法が、私には思考の省略か怠慢としか感じられないのだ。(P217)2014/12/27
NагΑ Насy
5
6章と7章。ラカン中村元『龍樹』柴崎友香。連載が5年以上前チェルフイッチュ『三月の5日間』川上弘美『真鶴』が新作だった頃。すこし昔の今の文章を読み現在を相対化できた。セミネール二巻から延々と引用を並べているページ。自我はア・プリオリに想定されるものではなく分析の結果から人生の履歴における象徴活動の総和として捉えることができる概念である、という内容の引用を読んで、グッときた。近代と現代を分けるのは意識の中心として自我、あるいは私というものをア・プリオリなものとしておくか否かにある?2013/12/08
おいしい西瓜
2
これは小説家が書いた小説論だが、読み味としては評論というより小説に近い。ふつう小説は先が分からない。だから読者は何が起こるのか、起こってそれからどうなるのかが気になって先を読み進めていく。この小説論も、著者が小説について考えたことをどんどん書いていく。書いたことからさらに考えが進んでまた書いていく。私はそれに振り落とされそうになりながら、ときには理解できない(しづらい)箇所を、それでも飲み込みながら読み進めていく。それはほとんど小説の面白さで、だから面白い。2025/03/25
-
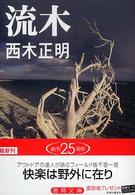
- 和書
- 流木 徳間文庫