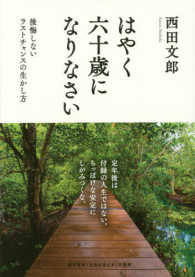内容説明
能の台本である謡曲は、美麗な文体で、人生を語り、人間の運命を様式の美しさの中で謡う。井筒、忠度、熊野、善知鳥、紅葉狩、高砂、隅田川、鉢木、江口、安達原等、10曲を口語訳で。能と深い関わりをもつ狂言はセリフ劇である。底抜けに明るく、ゆとりある笑いに包まれて快い。太郎冠者が大活躍し、逞しい庶民の女たちも登場する。狂言の魅力に現代語で迫る。中世の美意識と笑い、現代語の台詞とト書きで伝える能と狂言のエッセンス。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
57
貴族の娯楽であった能の台本である謡曲、農民の娯楽であった狂言を現代語訳。但し、謡曲集は馬場さん視点からの深読みもあるので純粋に謡曲を楽しみたい人には興醒めな所もあるかも。古野まほろ作品で出てきた「うとうよしたか」はそういう意味だったのね。「隅田川」は狂女と亡くなった子との邂逅が切なくも美しい。狂言の『柿山伏』は小学生の時、何かの本で読んだことがあるから、久々に出会えて吃驚しました。「髭櫓」と「木樽六」は爆笑。「月見座頭」は座頭さんの月見を楽しむ風流心にしみじみと感じ入ります。「菓争」は『山猫と団栗』かいな2017/05/26